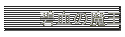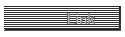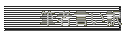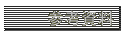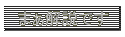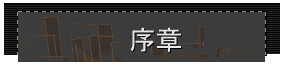
|
…まぁと一美、出会いの章… |
|---|
|
序 耳元でなにかが轟々と鳴っている。 それが、自分の吐く息の音だと、彼女が気付くまで、恐ろしく時間がかかった。 全身に脂汗。ひっきりなしに木の根や石くれに躓いて、足は痺れて感覚がない。 昼間なのに、なんて暗い場所! 仰げば針葉樹のはざまから、空は見えるけれど、青黒いばかりで光はない。 そして、彼女のいる木の下闇の底知れない深さ! 立ちはだかる木々は、どれも魔王のように巨大で、地面に付きそうなくらい下枝を垂らしている。そのとげとげしい黒いカーテンの中から、あいつはきっと自分を狙っている。 彼女は血走った目で、せわしく見まわす。礼拝堂はどこ! 不意に声が聞こえる。 「神は、お前など救ってはくれない。…『女は迷蒙、欺瞞、軽佻において男を凌駕し、肉体の弱さを悪魔と結託する事で補う。そして復讐を遂げる。妖術にすがって執念深き淫奔なる情欲を満たさんとする。奢覇都(サバト)は女たちの群れで埋め尽くされている―よもや魔女がいないとは言わせない』…そうだ、お前は…魔女に違いない!」 彼女は耳を押さえ、歯を食いしばる。激しく首を振る。 その時、彼女の目は、とらえた。 前方の、ひときわ巨大な針葉樹の根元に、それがいるのを。 目尻が裂けるほどに目を見張り、彼女は…
1 それは、明るい陽射しを浴びながら、昼休みの弁当を食べている少女たちには、まことに似つかわしくない話題だったかもしれない。 「ねえねえ、ほら、礼拝堂の裏手の森にさあ、黒い聖母が出るって噂、知ってる?」 「え―、なにそれ」 「顔も、手も、もちろん身体も真っ黒なマリア様なの…うん、木彫りの像だったんだって、元は…でもね、何時の間にか、魂が宿って、礼拝堂から抜け出して、森の中をさ迷ってるの。」 「やだ、それって怪談」「ずっと言い伝えられてるんだって」「中等部からいる子は皆知ってるよ。ただの言い伝えじゃなくて、実際に黒い聖母に呪われて行方不明になった子だっているんだから」「えー!」 「そう、あの礼拝堂の北側の森には、絶対入っちゃ駄目なんだよ。あの中で、黒い聖母に会うと、真っ黒な顔に真っ赤な口が開いて、咽喉から血を吸われるの。そして死体は礼拝堂の地下に引きずり込まれるんだって」 少女たちは、制服の肩をすくめ、教室の窓から見える礼拝堂と、その背後のヒマラヤスギの森を、不安げに眺めた。 「面白いじゃない、あたし、そういう伝説、好きだなあ」 笑顔で言いはなった花宮雅子に、回りを囲む少女たちは目を見張る。 「さすが、まぁ、度胸あるねえ」 「でも、そのお弁当のでかさ、なんとかなんない?」 一人が雅子の特大の弁当箱を指してしかめ面になり、少女たちはどっと笑い崩れた。 「花宮さん、野木先生がお呼びよ。職員室まで来てって」 不意に、冷たい声が割り込んだ。澄ました顔の少女が、教室の戸口に立っている。雅子が頷くと、ぶい、と顔を反らして歩み去った。
2 クラス委員に選ばれて以来、雅子は担任の野木哲也に呼びつけられて、あれこれと命じられることが多い。 (あたしが立候補したのは、野木先生にとって、よっぽど予定外だったのね。だから焦って、あたしがどんな風に使えるか、試したがってる) 職員室に向かう雅子の顔には、うっすらと苦笑いが浮かんでいる。 「失礼します。一年D組、花宮雅子です。野木先生に呼ばれて参りました」 職員室の入り口で一礼し、生徒手帳に書かれたとおりに挨拶の口上を述べた雅子は、振り向いた野木を、凛とした表情で見つめた。 二十代後半で独身、整った容姿の野木は、神経質に眉を動かしながら頷くと、雅子を招き、いきなりため息をついた。 「入学式から一ヶ月経って、やっとクラスも落ち着いたと思ったのに、ちょっと、困った転校生が来るんだ…、いや三日前に来てるはずだったんだが…」 「え?一年生で…転校ですか?」 首を傾げた雅子に、野木は手元のバインダーを持ち上げる。数枚の用紙が挟んであり、「編入調査票」と一番上に記されている。 「京都の美園(みその)女子高校に、去年入学した子なんだが、うちで一年からやり直すんだ。だから君たちより一歳年上だ。本当は美園で一年をダブってやることになってたのが、急遽、転校ということに…ほんとならこんな無茶はできないんだが、ほら、うちと美園は姉妹校みたいなものだからな」 「それが、三日経っても、まだ登校してこないんですか?」 雅子が訊くと、野木は自分の頭に手をやり、柔らかくカールした髪を、軽くかきむしった。 「そういうことだ。ゴールデンウィークに入ってしまう前に、なんとか不登校は解消したい。今日の放課後、やっと学校には出てくると連絡があった。面接するから、花宮も同席しろ。何か予定はあるか?」 「生徒会の用事がありますが」 「どうせ雑用だろう。断っておけ。それだけだ。」 野木は一方的に言うと、机に向き直る。雅子は少し呆れて、問いかけた。 「あの、どんな子なんですか?名前は?」 驚いたように振り返った野木は、しぶしぶバインダーをめくる。 「鳴滝一美というんだ。中学まではトップクラスの成績だったらしい。ところが、高校じゃ、何度か停学処分を受けてる。こっちではそうならないようにさせないとな」 聖アガタ女子学院は、中等部と高等部、そして短大で構成されているミッションスクールである。言うまでもなく生徒は女子のみ。中等部から短大までエスカレーター式に進学する生徒が大部分を占めている。 雅子は、この春、公立中学から高等部に入学した少数派である。彼らはどのクラスでもエスカレーター式進学者に圧倒されて大人しいのがふつうだ。だから、入学後一週間目のHRで、雅子がクラス委員立候補者として手を挙げたとき、クラスの全員と担任の野木が、目を点にした。 野木が学級委員に目論んでいたのは、エスカレーター派の優等生。彼女が、野木に目配せされつつ、下を向いてもじもじしているのを見て、雅子は敢然と立ち上がったのだ。 動揺した野木が「宮前はどうだ?」と名前まで出して促したのに、彼女(宮前香奈と言う)はついに立たず、ほとんどクラス全員が拍手して、雅子は無投票で学級委員になった。 (面倒なことはみんなあたしに押しつけに来る) と雅子は顔をしかめるが、誰からも頼りにされていることは間違いない。特に途中入学者たちからは姐御的に慕われて、他のクラスの子まで相談に来る有様。雅子は大勢に囲まれて賑やかに学生生活を送っている、ように見える。
3 午後の授業の間、雅子の脳裏を一つの言葉が占めていた。 (転校生…「さっすが転校生」「転校生だから成績優秀でスポーツも万能だって言うの?」「いちいち転校生の私のせいにしてさわぐのはやめて!」…) 二年前、あの転校生が現れてからの特異な出来事は、たぶん一生忘れられない。そして、彼女との葛藤は、まだけりが付いたとは言えないだろう。いまだに彼女の顔を想い出すたび、雅子の胸にはどうにも説明の付かない感情が渦を巻く。 今度、このクラスに迎える転校生には、二年前のような間違った態度で接するのだけは避けたいと、雅子は切望している。またしくじったら、せっかく上手くスタートした高校生活が、いや、これからの自分の人生が、壊れてしまうような気がするのだった。 そんな思いを巡らせて、知らず知らず爪を噛んでいた雅子は、不意になにかに肘をつつかれているのに気づいた。痛い!シャープペンの芯だ。右隣の麻田かれんの仕業だ。 (なにすんのよ、かれん!) 小声で叫んで睨もうとした瞬間、頭上から太い男の声が降ってくる。 「花宮あ、そんなにぼーっと考えごとしてるのは、彼氏でもできたのかあ?さっきから、十三ページを読んでくれないかとお願いしとるんだがなあ」 分厚いレンズの眼鏡をかけた古文の遠藤教師が、巨体を雅子の目の前まで運んで来ていた。 「す、すみませんっ!」 慌てて教科書をめくりながら立ち上がった雅子の隣で、かれんが色白の顔を赤く染めて「あちゃー」と顔に手を当てている。どっと笑いが起こった中で誰かが「クラス委員のくせに」と嘲笑しているのがはっきり雅子の耳に届いた。かれんや、沢渡礼子など、雅子に親しい生徒たちが、きっ!と敵意を込めて振り返る。雅子を嘲ったのは、窓際の一番後列にいる、北条寺美緒に違いない。 読み終えて着席するとき、雅子はちらっと美緒をうかがった。美緒は見事にカールさせた長い髪をもてあそびながら、まわりの生徒と小声で雑談を続けていたが、一瞬、雅子に視線を合わせた。美緒の形の良い唇が、きゅっと曲がった。優美な悪意の笑み。 雅子も微笑した。右頬に、魅力的なえくぼが刻まれる。だが、まだ美緒ほど洗練されてはいないと、雅子は自覚している。
4 古文の授業が終わると、たちまちかれんが雅子に肩を寄せてくる。無邪気な丸い瞳に心配と好奇心が同居している。 「まぁらしくないじゃん、ほんとに、彼氏でもできたの?」 「まぁに限って、それはないね」 少年ぽい声で否定したのは、席を立って寄ってきた沢渡礼子だ。ショートカットの頭を軽く傾け、机に片手を付いてまぁの顔をのぞき込む。そして小声で囁く。 「あーもう、美緒なんかをのさばらせておくの、がまんできないよ。早く潰しちゃおうぜ」 「わあ、さすがまぁの親衛隊長、かっこいい」 かれんが手を叩くまねをする。雅子は思いきり顔をしかめつつ、二人を手で追い払う。 「まだ、最後の授業が残ってんのよ。野木っち、予習してないとうるさいでしょ」 「いいよねえ、礼子は。二年前までニューヨークにいたんだから、英会話なんて予習も復習もいらないんだから」かれんが羨ましそうに礼子を見上げる。 「でも、テストでいい点が取れるとは限らないんだ、これが」 礼子は苦笑して席に帰っていく。 教室に入ってきた野木は、どことなくいつもと違って落ち着きを欠いていた。浮ついたその表情に、雅子は不意に、嫌な予感を覚えた。 生徒たちを見回すなり、野木はけいれん的に瞬きしながら、一気に言い放つ。 「授業を始める前に、転校生を紹介しておこう。ホームルームでもないときに唐突だが、早い方が馴染めるだろうと思う」 (え?放課後にあたしと先生とで面接するんじゃなかったの?) 雅子はうろたえるが、顔には出さない。 「はいりたまえ!」 野木が大声でドアに叫ぶ。…なんの反応もない。沈黙が続き、生徒がざわめき始める。野木の額に青筋が浮かぶ。もう一度叫ぼうと野木が口を開いたとき、乱暴にドアが鳴り、音を立てて開いた。 錐のように細い突風が、ドアから教室を貫いたような気がして、雅子は目を見張る。開いたドアから、長身の少女が、聖アガタ女子学院の制服に身を包んで進んでくる。 その少女の顔には、怒りがあった。固く唇を結び、目に強烈な光を宿していた。彼女の顔立ちは… (似ている!沙世子に、まるでそっくり) 雅子は即座にそう感じ、同時に涙ぐみそうになった自分に驚いた。 「美、美形じゃん」 となりでかれんが、賛嘆の声を遠慮なく上げ、それに同調する級友たちの声があがる。野木がわざとらしく両手を広げてそれを静め、黒板に向かってチョークを走らせる。 鳴滝一美 「なるたき、かずみというんだ。京都の美園女子高校から、家の事情で転校してきた。入学から一ヶ月で、みんなも落ち着いたところだし、余裕もって受け入れてやれるな?クラス委員の花宮と、副委員の宮前、とくにしっかり頼むぞ」 宮前香奈が、さっと立ち上がり、はい、と野木に頷く。 (なにを自慢そうに言ってんの)胸の中で毒突きながら、雅子は立ち上がり、野木を無視して、転校生に向かった。 「あたしが、花宮雅子です。一美さん、よろしく」 鳴滝一美は、じっと雅子と視線を合わせた。不思議な、煙るような目だと雅子は思った。第一印象と違って、彼女の顔立ちは、津村沙世子にあまり似ていないことに気づく。沙世子ほど、目はきつくない。顔の掘りもあれほど深くはなく、言って見れば和風に整っている。そっくりと思ったのは、その長く美しい髪のせいだろうか。
5 「詳しい紹介は、改めてホームルームでするとして…空いている席がないな」 野木が、しくじったという顔になる。 「クラス委員の二人、すまないが備品室に行って、机と椅子を…」 その言葉を遮って、ぴしり、と一美の声が響いた。 「私、今日は授業を受けるつもりはありません。話が違います」 気まずさが教室を満たす中、雅子だけが、一美の声に聞き惚れた。 (なぜ、こんなに特別にからだのなかに響くの?) 「この学校に転校したのは私の意志に反してます。それを説明したいと伝えたはずです」 「まだそんなことを…そのことについては君の保護者…成瀬さんと話が付いている」 野木の高圧的な喋り方に、一美は唇を噛み、髪を揺らして背を向ける。出ていこうとする。 とっさに雅子の口から、思いも寄らない言葉が出た。 「一美さん、京都の前には、どこにいたの?」 立ち去ろうとした少女の足が止まり、いぶかしそうに眉をひそめた顔が振り向く。雅子はえくぼを見せて、答えを待つ。一美のこわばった表情が、わずかに和んだように見えた。 「そんなことが…どうしてわかるんだ?」 野木が苛立って雅子に詰問する。邪魔しないで、と思いつつ雅子は一美に話しかける。 「だって言葉に訛りがないもの。何度か転校を経験してるんでしょ?」 話しながら、雅子は一人の少女の顔を想い出していた。その明るい顔が心に浮かぶといつも力が湧いてくるのだ。(あたし、今、玲の真似をしてる…) 「確かに…神戸とか、舞鶴とか、転校してるけど…どっちにしても、うち、関西弁なんよ、ほんまは」 いきなり一美のアクセントが変わったのに、教室が湧いた。 「わあ、あたし生の関西弁て、初めて聞くよお」かれんが目を輝かせる。 一美は、とまどっていた。雅子は畳みかけるようにとびきりの笑顔を向けた。 「ね、一美さん、案内してあげるから、あたしと一緒に机取りに行こう!」 野木が、救われたような顔で頷いている。香奈が無表情で戸口に立っている。雅子は進み出て一美の手を取ろうとした。 「うちは…」 一美が喋りかけた時、教室の後ろから、含み笑いの混じった声が響いた。 「ねえ、標準語喋れるんなら、標準語使って欲しいわ。あたし、くねくねしなしなした関西弁の女って、だいっ嫌いなの」 北条寺美緒は、腕組みをして上体を机に伏せ、鎌首をもたげるように顔を上げて、笑っている。 「うちはあ、京都のおなごはんどすう。お上品どすえ、ていねいにあつかっておくれどすう」 おかしなアクセントで、美緒が体をくねらせながら喋ると、周りの数人がけたたましく笑ったが、他の大部分の生徒は凍り付いた。 「やめなよ!北条寺」沢渡礼子が怒りで頬を染めている。雅子は慌てて一美の表情を窺った。 「どすどす言うの、やめてくれへん?うち、祇園や上七軒にいたんと違うよ」 低い声で一美が言うと、腹に響く迫力があった。 「…やっぱり、来るんやなかったわ」 言い捨てて一美は、きっぱりと雅子たちに背を向け、教室を出ていく。反射的に雅子は後を追っていた。
6 …自然体から思い切り遠くへ飛び、砦(とりで)を破る気迫で敵陣に突入。同時に攻撃を右腕で受けとめ、振り向いて後方からの攻めを左腕でブロック。閃くように右腕で中段への攻撃を防御し、再び正面に向き直ってさらに敵の鋭鋒をはね返す…こうして素早く受けを切り返したのち、騎馬立ちになり、右中段突き! 沢渡礼子は「抜塞(バッサイ)」の型を演じ、鋭く気合いを発して、右下段に蹴り込んだ。彼女の脳裏では、想像の敵が、足を骨折させられて悲鳴を上げている… 道場を持たない空手部は、テニスコートとバレーボールコートの間の通路で型の練習をしていた。入部して間もないが、先輩の誰よりキャリアのある礼子が既に部をリードしている。 汗を拭って顔を上げたとき、テニスコートの向こう側を、雅子が歩いてくるのが見えた。肩を落とし、ひどく意気消沈している。礼子はタオルとポカリスエットのペットボトルを掴み、身軽に通路の柵を飛び越えて雅子に駆け寄った。 「まぁ!今帰ってきたんだ。転校生追いかけてったきり、戻ってこないから心配したよ」 「うん、ごめん」 「飲む?」雅子があまりに憔悴した顔をしているので、礼子はペットボトルを差し出した。雅子はものも言わず、一気に500mlを飲み干してしまった。礼子は呆れる。 「どうしたんだよ?」 「なんでもない、野木先生に報告して、生徒会室にいかなきゃ。あああ、怒られるよお」 それだけ言って駆け足で去る雅子を、礼子は物足りない顔で見送った。気さくになんでも話しているようでいて、雅子は友達の誰にも心をフルオープンにはしていない。親友を自認しているかれんにも、他校から編入した同士、連帯感を抱いている自分にも… 唇を尖らせたまま、着替えを終えて校門に向かう。突然、礼子の前に、人影が立ちふさがった。 「沢渡さん、ちょっとつきあってくれない?」 丁寧にカールさせた前髪の陰から、切れ長の瞳が笑みを含んで輝いている。礼子は息を飲んで立ち竦み、知らず知らず拳を握りしめている。
7 自分の部屋に戻った雅子は、通学鞄を床に落とすと、制服のままベッドに仰向けにひっくり返った。 (なんか、ひどく疲れた…) …教室を飛び出した一美を追い、雅子は校舎を出た。一美は足が速い。学院のメインストリートと言うべき桜並木で、息を切らして追いつく。 「待ってよ、一美さん」 「授業に戻れば?クラス委員さん」 一美は呼吸を乱さず、涼やかな眼差しで前を見たまま、歩みをゆるめない。あっと言う間に校門に近づく。 「だめだよ、警備のおじさんがいるし、鍵がかかってるんだから…」 雅子の言葉に、一美は耳を貸さない。怯む色もなくまっすぐ門に向かう。 不意に雅子の視界がぼやけた。一美の後ろ姿が揺らぐ。キーンという耳鳴りの中、重い鉄柵がごろごろと動く音が、微かに聞こえる。 目眩と耳鳴りから立ち直ったとき、一美の姿はどこにもなかった。驚いて警備室の中を覗く。紺の制服を着た初老の門衛は、パイプ椅子にのけぞって、口を開けて居眠りをしている。雅子は駆け寄って、鉄柵に手を掛けた。びくともしない。 歯がみして、雅子は鉄柵に続く生け垣に沿って走る。枝が粗くなっていて、遅刻したときや買い食いに出るときに生徒が潜る、公然の秘密の出入り口があるのだ。 肩や髪に葉っぱやら蜘蛛の巣やらをひっかけて、雅子は生け垣を突き抜けた。せわしく首を振り、一美の姿を探す。意外にもほんの十メートルほど向こうで一美が振り返り、目を丸くして雅子を見つめていた。 「なんで追いかけてくるん?」 「ねえ、どうやって門から出たの?」 一美は目をそらし、歩き始める。雅子は肩を並べて話しかける。 「あの柵、電動スイッチでしか動かないんだよ。もしかして一美さん、凄いパワー…」 ちらっと動揺を見せながら、一美は話を逸らした。 「どうして名前で呼ぶの?花宮さん。さっき会ったばかりなのに」 「あ?馴れ馴れしくていやなの?じゃあ鳴滝さん」 「別に、一美でええけど…無駄やで、連れ戻そうとしても」 とりつく島もなくさっさと歩いていく一美に、必至で歩調を合わせながら雅子は笑みを浮かべる。 「クラス委員としては、みんなが楽しく学校生活を送れるように努力しなくちゃ」 「やりたい人だけで楽しくやっとったらええやないの」 下り坂になり、一美の足はますます速度を増す。学院の長大な生け垣が切れて、商店街に入った。 「みんなで楽しくやるにはね、一美さんが必要なの」 「え?」 一美の足が止まったのは、商店街の真ん中あたり、小さな地蔵の祠の前だ。 「うちが必要て…なんでやの?」 「うん…そうだなあ、立ち話ってのは、嫌じゃない」 雅子は辺りを見回す。平日だが、すでに午後三時を回っているので制服でもそう人目には付かないだろう。(続く)
8 小さな喫茶店を見つけて強引に一美を引っ張り込んだ雅子は、ミルクティーを前に、真面目な表情を作った。 「あたしも、一ヶ月前は転校生みたいなもんだったの。入試って言っても、編入だから。クラスの子は大部分が中学時代からの顔なじみ。あたしと礼子含めて、編入は七人」 「礼子って、あのショートカットの、武道やってそうな…」 「よくわかるね!お父さんが空手の先生で、ニューヨークで道場開いてるんだって」 「それで、うちをからこうた人は、中学からエスカレーターで来てる子たちの…ボスやろね。」 コーヒーを一口啜って、一美は壁のユトリロの複製を見上げている。 「ボスって言うか…どうかな。北条寺さんていうんだけどね」 「うちに絡んだっていうより、そうか、花宮さんへの嫌がらせか…」 一美の洞察力に、雅子は舌を巻いた。 「あんなちょっとの時間で、すごいねそこまで。じゃあ、わかってもらえるかなあ。あたし、一人でも味方が増やしたいんだ」 雅子は熱意を込めて瞳をきらめかせる。 「あたし一人の力なんて知れてる。頼りになる人が欲しいの。エスカレーターとか編入とかそんなこと関係なしに、やっていきたいじゃない。ほとんどの子は、そう考えてると思う。でも行動に移すのはみんな億劫。確信もって動く人についていく方が楽だからね。北条寺さんは…破壊の確信犯、かな」 一美は、意外そうに目を見張り、雅子に向かって、初めて笑った。 「クラス委員さん、あんたも、結構過激なんや」 「北条寺さんに比べればたいしたことないよ。なんでも、壊したいのよ、美緒は」 クラス委員に立候補した雅子に、まっさきに拍手したのは美緒だった。宮前香奈と野木先生に恥を掻かせたかったから。雅子がクラス委員として活動を始めると、今度は当たり前のように妨害を始めた。 「美緒ってすごく頭はいいのに、勉強はしないの。テストもまともに答案書かないそうよ。でもほとんどの先生は美緒には何も言わない。飛び抜けて親の寄付が多い子だからだって。小学校の時、雑誌の読者モデルとかに選ばれて、今もどっかのモデルクラブに所属してるらしいけど、そっちも熱心にやってるようには見えない。ただ一つ情熱を見せるのは、人やものを壊すこと。」 美緒のことを話す雅子の顔は、能面のように表情を殺している。一美は、視線を逸らして、またユトリロを見上げた。 「嫌やな、人間て」
9 何かに取り憑かれたような話し方をしていた雅子は、我に返って一美に身を乗り出す。 「だからね、一美さんにも力を貸して欲しいんだ。一目見て、頼りになる人だって…」 「人が、みんな自分の仲間だと思うたら、大間違いやで」 一美が歌うように言う。一瞬怯んだが、雅子は言葉を重ねる。 「でも、友達になる努力はしなきゃ。あたしは、一美さんと友達になりたいよ」 「クラス運営を円滑にする、手ゴマを増やすために?」 「違う!全然違うよ!」 上手く自分の気持ちを表す言葉が見つからず、もどかしさに雅子は爪を噛む。 「そういう、政治みたいな、主導権争いみたいなのに、首つっこみとうない。狭い教室で机と椅子に縛り付けられる意味もようわからへん。ごめん、うち、役にたたへんわ、花宮さん」 狭い教室で机と椅子に…一美が口にした言葉が、雅子の中で懐かしくこだましている。そんな言葉をいっぱい台本に書いて、全校生徒に読ませたことがあったっけ… コーヒーを飲み干して、一美は席を立とうとする。とっさに彼女の手を、雅子はテーブルに押さえつけた。 「もったいないよ!学校生活でしか味わえないおもしろさっていっぱいあるじゃない。一人でいることなんか、大人になってからいくらだってできる。学校に来ないで、何をするの?閉じこもって漫画とテレビだけが友達?」 「うちに、さわらんとって…放して!」 悲鳴に似た一美の叫びが、またしても雅子に既視感を抱かせた。それは後悔と畏れを伴っていた。電撃を受けたように、雅子は一美の手を離す。 (あたし、また、間違ったことをしてる?) 振り向かずに一美は店を出ていった。勘定を払って雅子がドアを抜けたとき、通りのどこにも一美の姿はなかった。 学院に戻り、礼子にポカリスエットをもらい、野木に叱られ、生徒会の先輩にも小言を言われたが、ほとんど雅子は覚えていない。一美が自分の手を振り払った時の、心の痛みが、ずっと続いている…
不意に、通学鞄の中でジムノペディのメロディが流れ始めた。携帯電話の着信音だ。ベッドの上に起きあがり、雅子は顔をしかめる。多分かれんからの長電話だろうが、応対する気力が今はない。 渋々手を伸ばし、息絶え絶えに携帯をとりだして、そのまま床に伸びる。 「はい、ただいま、まぁはブラックアウトしております」 「なあに、死にそうな声だしてんのよ?久しぶりだってのにご挨拶ねえ…」 「み、溝口い!?」 素っ頓狂に叫び、雅子はバネ仕掛けのように跳ね上がった。
10 先に立つ人影は、学院の中心にある礼拝堂に向かう。礼子の眼前に、高い尖塔が聳えてきた。規模は小さいものの、本格的なバロック建築様式で建てられた、学院自慢の建物だが、陰気くさい雰囲気で礼子はあまり好きではない。 「え?そっちへ行くのか?」 思わず口にした礼子の言葉に、人影は振り向いて、白い歯を見せて笑う。 「なに?カラテガールでも怖いの?そうよねえ、もうじき夜だし」 「馬鹿馬鹿しい!闇の聖母だか、ブラックマリアだか、あたしはそんな迷信、興味ないよ」 そう胸を張ったが、礼拝堂の北側の森に踏み込んで行く礼子の脚どりは、明らかに重い。 「ねえ、何の用だよ?」 先を行く背中に、礼子は我慢できずに声を掛けた。 「もう、誰にも話は聞こえないだろ?この辺でいい」 人影は、含み笑いをしながら振り返る。長い髪に縁取られて、その顔は暗く翳り、表情が全く見えない。 「何の用事だか、当ててごらんよ」 からかいの声に、礼子はかっと耳たぶまで熱くなった。 「まぁに肩入れするのをやめろって言いたいんだろ?そうはいかない。こっちこそ、いい機会だ。これ以上まぁにくだらない嫌がらせすんじゃねえよ。北条寺!」 「北条寺、か。そんな名前、何の意味もない。あの家に生まれたこと、この腐った世界に堕とされたこと、みんな間違いなんだから」 「なんだって?」 礼子は、理解できない言葉を紡ぎ始めた人影を、唖然として見つめる。 「ねえ、この世界は、ちっぽけな学院の中から、地球全体に至るまで、ぜーんぶ腐ってんの。知ってる?校長や理事長は寄付金をじぶんのものにして好き勝手に使ってるし、シスターの福永はレズだし、担任の野木は、香奈をセクハラしてるし…」 人影は呪詛のように言葉を続ける。 「…交通事故で一万人、自殺で三万人、日本で一年に死んでる人の数よ。あたしたちが、マックのハンバーガーを一口かじって捨てるその日に、アフリカや北朝鮮じゃ、何人が餓死してるんだろ。子供のミルクも買えない国が、アメリカやロシアや中国から、武器を輸入して内戦で殺し合ってるの。ねえ、神様は何をしてるんだろねえ」 「なに言いたいのかわかんないけど…神様の悪口、言うのは冒涜だよ…」 礼子は眉をひそめる。ニューヨーク時代から日曜には教会に欠かさず通ってきたのだ。 「あははは・・馬鹿じゃないの、冒涜なんて、この学院じゃ教師やシスターが率先してやってる。それでも神様は許し賜う。世の中には理不尽と残酷と無慈悲がまかり通る。それでも神様は何も手を出さない。あたしは、ずっと不思議だった。けど、やっとわかったんだ」 思いも掛けない相手の言葉に、礼子は口を挟めない。 「この世界にいる神様は、神様じゃないよ。悪魔だよ。この世界は、悪魔が作って悪魔が運営管理してるんだ。だから、神様に祈っても何も願いは届かない。それに気づいて、あたしは、悪魔に願ったの」 「何を願ったんだ」 礼子は、じりじりと身構えながら尋ねた。相手の意図が全く分からないが、恐ろしく危険な雰囲気が身体を締め付け始めている。 「無力な小娘だったあたしに、力をお与えください。毎晩あたしを犯しに来る父を叩きのめし、威張りくさっている祖母を老人ボケにし、意地悪なバレーボール部長を事故に遭わせ、家でも、学校でも、あたしを馬鹿にする奴が一人もいないように、あたしに力をくださいって」 礼子は、完全に言葉を失い、人影の、赤い唇を見つめるばかりだ。 「この学院にはね、いたの。あたしを悪魔に仲介してくれる魔法使いが。そして、ほらあんたの後ろに聳える礼拝堂、あそこは、悪魔の宮殿なのよ…。沢渡礼子さん、ここまで打ち明けたんだから、あたしの言いたいこと、わかるでしょう?そう、あなたにも、仲間になってもらいたいの」 「…なかま?」 かろうじて礼子はオウム返しにうめく。 「あなたがあたしを気に入らないのは知ってる。でもね、花宮雅子に近づくのは、大きな間違い。あの女と一緒にいるなら、あたしはあなたも、もろともに、壊すよ」 「えい!何をだらだらと、訳の分からないことを喋ってんだ。私は、まぁの友達だよ、まぁを壊すなんて、絶対許さない。あたしがまぁを守る」 礼子は、ゆっくり後屈立ちの姿勢をとりながら、叫んだ。 「しかたないな…少しだけ、あたしの力、見せたげる」
11 ベッドに腰掛け、雅子は携帯電話を握り締めて笑顔になっている。 「また、どうして電話なんか…携帯持った時は喜んで、山ほどメール送ってきたよね、溝口」 「慣れない女子校であんたが寂しいと思って…そんなことどうでもいいわ。あんた、今日、あたしのなじみのお店に来てたのよ」 「え?…あそこ、溝口の…ひょっとして、あの喫茶店に、いた?」 「そう。カウンターの隅っこがあたしの定位置。まあ、なじみって言ったって通いはじめて一ヶ月くらいなんだけどね。それにしても、また、派手顔の子と一緒だったわね」 派手顔…今日は懐かしい言葉を何度聞くだろう。 「なんか、マジな話してるみたいで、声掛け辛いと思ってたら、喧嘩別れして出てっちゃって、ちょっぴり気になったのよ。べつに、まぁが誰とつきあおうと別れようと、あたしにはどうでもいいんだけどね」 「あのねえ、つきあうだの別れるだの…あの子、ついこの間、うちのクラスに転校してきた子なんだよ。でもかなりトラブルがあって、クラス委員としては放っておけなくて…」 「授業を抜け出して喫茶店で相談ってわけ?優等生のまぁにしては、やるじゃない。見直しちゃう」 「あんたに見直されても嬉しくないけどね。あ、そう言えばあんたこそ、学校さぼってサテンに入り浸りなわけ?言いつけちゃおうかな」 「なによ!せっかく人が心配して励ましの電話をしてるのにい。ああ、損しちゃったわ」 「わりいわりい。…ごめん、嬉しかったよ。ほんとは」 「え?何が?」 「あたし、ちょっと…すごく落ち込んでたんだ。また、しくじっちゃったって。溝口の声聞いたら、ちょっと元気が出たみたいだよ」 「またしくじったって…、ひょっとして前の派手顔さんと同じみたいに?また、転校生相手に、ま、まさか、魔女裁判をやったとか」 「やってないよ!」 溝口の口から出た、魔女裁判という言葉を、雅子は金切り声で否定して、自分で「はっ」とする。 「び、びっくりしたわあ。そんな声で怒鳴らないでよ」 「あたし、もう、絶対あんなこと、やりたくない。もう、あんなあたしはやめたんだ。でも、今度の転校生にも、うまく接することが出来ない…」 「ちょ、ちょっと待ってよ。そんな深刻になるのはやめ!あたしが悪かったわ。昔のやな出来事想い出させちゃって。あたしらしくもない無神経だったわ」 「溝口だって、あのとき無神経に、沙世子を怒らせたくせに」 「だから、あのときの話は、なし!…でもやっぱり、今度の彼女、沙世子を思わせる女の子なのね?」 溝口の、まじめな声に、雅子はしばし沈黙した。(まだまだ続く)
12 成瀬、と表札のかかった、小さくて古いけれど清潔な洋館である。 鳴滝一美は、玄関からまっすぐ廊下を進み、重い樫の木のドアを軽々と押し開いて、リビングルームに歩み入った。「突入」と言ってもいい勢いだった。 「お帰りなさい、一美」 成瀬奈津が、柔らかい笑みをたたえて振り返る。老女の優しい目を見ると、一美の意気込みは崩れそうになったが、かろうじて踏みとどまり、鋭い声を、奈津が押している車椅子に浴びせかける。 「おじいちゃん!なんで、うちをあんな学校へ行かせたがるんや?義務教育だけでたくさんやて、うちはずっと言うてきたやん。うるさいパパやママも、美園でうちが暴れたんで、あきらめてくれはったのに。おじいちゃんが、関東に来い言うてくれはったんで、てっきりうちの気持ちが分かってくれてると思うてたのに!」 いきり立つ一美に、奈津が笑って首を横に振る。一美はあっと小さく叫んで、車椅子の前に回った。 赤い毛布を膝に掛けた痩せた小さな老人は、気持ちよさそうに首を傾げて、軽いいびきをかいている。皺だらけではあるが、童子を思わせる無邪気な表情だ。 「まったくもう!いっつもうちが話をしたいときは寝たふりこいて!この狸爺い!」 地団駄踏む一美をなだめるように、奈津が肩を叩き、車椅子を押してテーブルに向かう。紅茶の支度がしてある。 「まあ、お飲みなさいな。気分を落ち着けなさい」 「おばあちゃん、なんで、うち、学校へいかなあかんの?行ってはらへん人、一族には仰山いてはるやん?」 「この人の言うことではね。一美にはまだ学校生活が必要なんだって。一族以外の、普通の人間ともっともっと心を通じ合わせないと、一美のためにならないと、私も思いますよ」 「そんなん…無理やわ。パパやママもそう言わはるけど、パパたち自身が、普通の人たちとろくにつきあってへんくせに」 一美は、口惜しそうに呟くと、立ったままティーカップをあおる。絶妙の煎れ方のアールグレイが、一美の熱した頭に涼風を吹かせる。 「ごちそうさま、その狸爺いが起きはったら、教えてね、おばあちゃん」 「さあ…しばらく目を覚ましませんよ、不二彦さんは。午前中から、ついさっきまでお仕事をなさってらしたから」 奈津は暖かい視線で、夫の成瀬不二彦の寝顔を見守る。一美は舌打ちをする。 「仕事…って、また与党の大物とかに頼まれて、予知能力使わされてたん?無駄遣いやわ。うちら一族の力で革命でも起こした方が早いんと違う?」 「これ、一美。不二彦さんのお仕事をとやかく言うのは、僭越というものです」 初めて奈津が厳しい表情になり、一美は首をすくめて自分の部屋に退散した。 制服を普段着に替え、じっと鏡を覗く。そっと自分の手を見る。さっき、花宮雅子と言う少女に握られた感触が、まだ残っている。彼女の掌が触れた瞬間に、その感情が焼き付くように伝わってきた。 (あったかい…とてもあったかい、あれは、友情?友愛?) 一美は戸惑う。なぜさっき初めて出会った自分に、雅子はそんなにも… (そして、そのあったかさのなかに、痛いほどの後悔と、深い畏れがあったのはなぜ?) 頬杖を突いて、一美は考え込む。真ん中から分けた、くせのない長い髪が肩から腰のあたりにまで流れる。宵闇の中で、その横顔は聖女の肖像のように清らかだ。
13 暗黒の森の中、地面に倒れた少女の血塗れの手を、革靴がさらに無慈悲に踏みにじった。沢渡礼子は苦痛のうめき声を漏らした。絶望感が彼女の胸を塞ぎ、礼子はがっくりと顔を地面に伏せた。革靴は、針葉樹の厚い落ち葉を踏みながら、遠ざかっていく。 礼子は力を振り絞って、通学鞄に這い寄り、痺れた手を突っ込んで、携帯電話を取り出そうとする。うまく掴めず、何度も中身を探って、やっとのことで引き出した。 他の指は使いものにならないが、親指だけは両手とも健在だ。暗闇の中でも、間違いなくボタンを押し、メモリーした番号をかける。 「ああ…まぁ、なんでこんなときに、お話し中なんだ」 無念さに、礼子はすすり泣く。泣きながら、次の番号を押す。明るいはしゃいだ声が出た。 「はあい!まぁでしょ?いったい誰と話してたのよ、あたし以外と長電話なんて許せない」 礼子は、しゃくりあげながら、麻田かれんのおしゃべりを遮る。 「かれん…あたしは、礼子。やられた…やられちゃったよ。あたし、動けない…助けに来て…まぁに伝えて…礼拝堂の裏にいるの」 とぎれとぎれに、それだけ喋って、礼子は力つき、携帯電話を地面に落としてしまう。その時、礼子の耳に、奇妙な声が聞こえてきた。濁った、太い、男の声。それは、暗い森全体に、密やかに響きわたった。 「バガビ、ラカ、バガビ、ラマク、カヒ、アカバベ、カルレリオス、ラマク、ラメク、ガカリアス…反逆の王、ルシファーよ、我を憐れみ、今宵大いなるしもべを我に使わし賜え」 それに応えるかのように、ヒマラヤ杉の根本で、吼え声が湧き起こった。そこには、礼子が北条寺美緒だと認識していた、あの人影が、天を仰いで、野獣のように吼え猛っている。その影は、次第に変形していく。人の形でなくなっていく。 礼子は倒れたまま、目を見開いた。その瞳には、恐怖しか映っていない。切れて膨れ上がった唇をいっぱいに開けて、礼子は言葉にならない絶叫を放った。 そのすさまじい悲鳴は、転がっている携帯電話にも吸い込まれた。
14 雅子は、居間から聞こえる母の声に、我に返った。 「雅子、電話よ。麻田さんのお母さんから」 かれんのお母さん?雅子は首を傾げた。 「あ、溝口ごめん。ママが呼んでるし、またね」 「ん、元気だしてね。またあの派手顔の転校生、お店に連れてらっしゃいよ。興味湧いちゃった」 「もう!相変わらず野次馬なんだから」 携帯電話を鞄にしまい、雅子はスカートの皺を治しながら部屋を出て、居間の電話の子機を取り上げる。 「はい、花宮雅子ですが、初めまして」 「あ、まぁさん、ですよね?かれんがいつもお世話になってます…」 なんだろう?相手の声の調子がひどく緊張している。異常を感じて、雅子は子機を強く握りしめた。 「かれん、どうかした…いえ、かれんさん、どうかなさったんですか?」 「それが、ついさっき、携帯電話で話していたらしいんですが、突然興奮して、ひどく怯えてしまったんです。まるでちっちゃな子供みたいに泣きじゃくって」 雅子は胸が締め付けられるように苦しくなってきた。 「とりあえずベッドに寝かせて、かかりつけのお医者様を呼んでるんですけど、かれんが、うわごとみたいに言い続けてるんです。『くろいセイボ、くろいセイボ、まぁに知らせなきゃ』って」 「え?うわごと…黒い聖母!?」 「あ、それから、『レイコが、ちをすわれた』ってことも、ひどく怖がって言うんです…あの、何かお心当たり、あります?」 「礼子は…私たちのクラスメイトです。」 「とにかく、死にものぐるいで、まぁさんに知らせてくれと言うものですから。自分では電話に触るのが怖いみたいで…じゃあ、ごめんなさいね」 伝えるだけは伝えたという口調で、そそくさとかれんの母は通話を切った。雅子は子機を持ったまま、立ちつくした。
15 呆然としていたのは、しかし、数秒のこと。額の汗を拭うと、雅子は自分の部屋に向かう。改めて携帯電話を取りだす。 礼子の携帯…「通話できない状態になっております」と案内音声が返るばかり。 礼子の自宅の電話…誰も出ない。 雅子は、しばらく躊躇してから、ためらい勝ちに次の番号を打った。 「はい、ジョリ・フルールです」声変わりはしているが、まだ少年らしいその声…、いきなり本人が出るとは思わず、雅子はごくりと唾を飲んだ。 「あの…由紀夫…ユキ?」 「まぁ?おい、まぁかよ!なんだよ、随分ほったらかしにしてくれたよな、元気?」 屈託のない、嬉しそうな少年の声に、雅子の顔が泣きそうに歪む。
それから数十分後、雅子は聖アガタ女子学院の門の近くで、制服姿のまま、電話ボックスにいた。既に門の中は黒々とした闇に包まれ、門衛室の明かりだけが寒寒と点っている。 肩を竦めた時、ボックスのドアが軽く叩かれた。ガラスの向こうに、唐沢由紀夫の背の高いシルエットが浮かんでいる。雅子は素早く外に出た。 「ありがとう!また、ユキにこんな無理たのんじゃって。でも、あなたしか…」 「いいんだよ。まぁの頼みは、いつだって断れない俺だもん。しかし、夜に女子校に忍び込むなんて、ドキドキするよなあ」 「ばか、声が高いよ!」 既に正門のきわまで来ていた雅子は、慌てて由起夫の口を塞ぐ。由起夫はどぎまぎして頷き、雅子の手の感触に顔を赤くする。雅子はそんな由起夫の手を握って、必死に生け垣の秘密の出入り口に身体をねじ込む。雅子は制服のままだが、由起夫は黒のトレーナーにジーンズという服装だった。 中央棟の職員室を中心に、明かりがついている他は、どの校舎の窓も黒く沈み、通路もグランドも静まり返っている。雅子は懐中電灯を握りしめて、由起夫を引っ張りながら、礼拝堂を目指した。尖塔の頂の十字架が、夜空にくっきりと聳えていた。 「うわ…こんな森があんの…向こうが見えないじゃん」 由起夫が露骨に恐れをなした。 「でも、この中にきっと、礼子がいるんだ」 雅子はきっぱりと言って、懐中電灯を点けた。ヒマラヤ杉のびっしりと茂った枝葉が闇の中に浮かび上がる。その光の輪を下に向け、雅子は踏み出す。地面の感触が異様だった。まるで足裏に感覚がない。(「地に足が付いていない」って、こんな事を言うんだろうな)雅子はそう思った。 「中学の北校舎じゃ、不甲斐なかったけど、今夜はガッツ見せてやるよ」 不安を紛らす為か、由紀夫は軽口を叩くように、そんな事を囁く。雅子の胸に、遠い痛みが蘇る。あの時、自分は由紀夫を危険な目に遭わせた上に、その存在を忘れた。信じられないほどひどい女の子だった… 雅子は由起夫の手を握りしめ、顔を伏せてうめいた。 「ごめん、本当にごめんなさい。あたし、ユキに助けてもらう資格なんかない…」 由起夫は唇を噛んで自分の言葉を悔いた。無言でただ、雅子の手を握り返した。由起夫の暖かく、力強い掌の感触がなかったら、きっと自分はこの黒い森に踏み込む勇気はないだろうと雅子は思った。 その時、懐中電灯の光の輪に、口の開いた通学鞄が浮かび上がった。ギク!と雅子の手が止まり、そろそろと光の輪を移動させる。 まるで胎児のような姿勢で、ショートカットの少女が地面に転がっていた。血だらけの手で頭を抱え、膝を固く胸に付けて、微動だにしなかった。由起夫が息を飲む音が、雅子にはっきりと聞こえた。
16 …闇の中から、雅子と由起夫を見つめつつ、密かに会話を交わすものたちがいる
「…あの少女がそうなのだね」 「ああ、間違いない。最初はただのいい子ぶった、その実目立ちたがり屋の軽薄な奴だと思ったけど」 「真摯で健気で、献身的な少女だね。べそをかいてはいるが、なかなか判断は冷静だ。少年に隠れるように言って、携帯で学校の職員室に連絡を入れている。カップルで発見者になるわけにはいかないからね」 「そうね、男を学院に引き入れたことがわかったら、あいつは退学。男も無事では済まない」 「どうするんだね。そういう目に遭わせることもできるが?」 「そんなの駄目。あいつは、もっとあたしの目の前で苦しめて、あたしの手で滅ぼすの」 「そんなにも、彼女は君にとって重要なのかい?」 「そうだ。あたしのただ一人の本物の敵。そしてたぶん、ただひとり愛することの出来る者」 「…愛する?」 「そう、愛する」 「…なんだ、ただの足手まといだね、あの少年。木陰に隠れて震えているだけじゃないか」 「あれでも、あいつの掛け替えのない人間の一人なのよ。今はあの男があいつの気持ちを支えている」 「幸福な少女だな」 「そう、その幸福を、あたしは全部壊してやる。そして…」 |
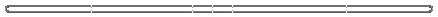
Copyright(c) 2003 龍3. All rights reserved.