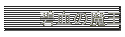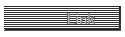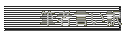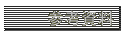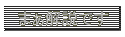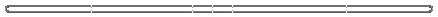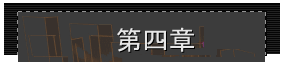
|
第4章・少女変身 |
|---|
|
50 聖アガタ女子学院の正門。まだ登校する生徒はまばらだ。一晩降り続いた雨はあがっているが、空の雲は厚い。重苦しい何かが、頭を押さえつけてくるようだ。 雅子は、背筋を伸ばし、まっすぐに歩き続ける。門が近づくと、そこに待っていた少女が、顔を上げ、雅子を見つめた。まだ包帯を巻いている手を挙げて、沢渡礼子は雅子に笑いかける。 「おはよう、眠れた?」 「礼子、おはよう。うん、長―くお風呂に入って、いっぱい汗流して、バタンと寝ちゃった。…一美さんは、まだ?」 「まだだけど…あ!かれんが来たよ!」 振り向いた雅子の目に、停車したプリウスから降り立ち、息せき切って走ってくる麻田かれんの姿が映る。 「会いたかったよお、まぁ!」 抱きついてくるかれんを支えかね、小柄な雅子は悲鳴を上げる。 「かれん、あんた、太ったんじゃないの?!」 「久しぶりの感動の再会に、それはないよお、まぁ」 礼子が笑ってかれんの肩を叩く。 「いつもいつもパパに送って貰うからだよ、徒歩で登校せい!歩いて脂肪を燃やすのだ」 はしゃぐ三人。雅子の目が、ふと止まり、いったん真顔になった表情が、ゆっくりとほころぶ。 「おはよう、一美さん」 長い髪を微かな風に揺らして立つ鳴滝一美は、雅子たち三人をまぶしそうに目を細めて見ている。 四人は肩を並べて校門に踏み込み、胸を張って教室に向かった。
「鳴滝、反省文は、これからすぐに、学院長室に持って行きたまえ。それから、花宮も一緒にとのことだ」 野木の言葉に、何故か教室がどよめく。その意味がわからず、一美と雅子は顔を見合わせた。礼子も不審な表情だが、かれんは他の生徒とともに、驚いた顔をしている。 野木は、それだけ告げると出席簿を小脇に立ち上がる。朝のショートホームルームが終わり、これから第一時限が始まる所だ 「授業には遅れてもいいんですか?」 雅子が野木を引きとめようと声を張り上げる。野木は歩みを止めず、首を回して頷いただけだった。 眉をひそめ、首を傾げて、一美と雅子は席を立つ。北条寺美緒は登校していない。彼女だけが無断欠席だが、他に病気欠席が十人以上いて、教室はやけにがらんとしている。 かれんが雅子を追い掛けてきた。 「まぁも一美さんも知らないと思うけど、学院長先生に会うって、事件なんだよ。だって、あたし、この学院に入って以来一度も見た事ないの。あたしだけじゃない、たぶん今学院にいる生徒と先生は、誰も」
51 かれんから、学院長室の場所を聞いた雅子は、一美と肩を寄せるようにして、静まり返った廊下を歩く。なぜか、二人の道のりがどこまでも続くような気がする。 「美緒、学校に来てなかったね。ちょっと安心したけど」 「気を抜いたらあかん思うわ。野木先生の様子もなんか変やし、かれんの言うことによれば学院長もなんやら、謎の人物やん?」 甘えるような雅子の声に、一美は冷静な表情を崩さない。渡り廊下を越え、職員室や校長室のある管理棟に到達する。学院長室はここの最上階の一番端にあるという。 何千、何万という足が踏みしめたであろう、すり減った木の階段を登り詰めると、どことなく埃と黴の匂いのする最上階だった。突き当たりの小さな木のドア。聖書の登場人物らしい彫刻が一面に彫られた扉だが、磨滅と埃でどれが誰だかよく分からない。一美は白い拳を挙げ、高らかにノックする。 「1年D組、鳴滝一美です」「同じく、クラス委員の花宮雅子です」 「入りなさい」 聞き覚えのある、男の声。一美と雅子は顔を見合わせ、ドアを開ける。 高い天井の、狭い部屋。古い書物の詰まった本棚が壁を埋め、どっしりした机と椅子がある。そして、部屋の中央には、天蓋つきの木のベッド。その横に、古典教師遠藤が立って、分厚い眼鏡を通して、少女二人に視線を向けている。 「どうして、遠藤先生が」 「いはるような気がしたで、遠藤先生」 雅子と一美の言葉は対照的だった。遠藤は苦笑し、二人を招き寄せる。 「話は手短にしよう。君たちを呼んだのは、他でもない、この学院を壊そうとしている魔女について、共同で対策を練ろうという、学院長のご意志だ」 「これは、じゃあ、どうでもええんや…せっかく徹夜で書いたんやけどな」 一美が、手に持った反省文の原稿用紙をひらひらさせる。雅子は緊張して、ベッドの中を窺う。小柄な人物が、羽布団にくるまっているようだ。 「学院長は、長いこと病んでおられてね。普段はご自宅で療養中だが、今日は特にこの問題で、登校されたんだ。私は…この学院では、こういった表に出来ないトラブルの解決の専門家…とでも言うべき職務を負っている。職員名簿には載っていない役職だがね」 一美は、反省文を机の上に投げてから、遠藤に近づき、眼鏡の奥の目をのぞき込む。 「全部情報を明かしてもらえます?魔女のことは、とっても危険なお話やと思います。うちら、既に命がけの経験してる。遠藤先生の手の内も、ぜえんぶ見せてもらわな、信用できません」 「もっともだな…私の負っている職務は、『ノワール』と呼ばれている。もっともその名を知っているのは、校長に教頭、学年主任、そしてここにおられる学院長くらいだ。私は何代目かは知らない。ノワールはいっさい文書を残さずに受け継がれてきた影の職務だからね。北条寺美緒は、二年前に、私がノワールの仕事として、妊娠中絶を受けさせたよ」 「それから、美緒は変化したいうんですか?」 「そうだ。あの子は、胎児を陶土と混ぜて勾玉にし、身につけるようになった。それから、恐るべき存在に変身していった…」 一美と遠藤の会話を、雅子は息を飲んで聞くしかない。なぜか嫌な予感が全身をさいなんでいるが、それがなにに由来するのかまったくわからない。 「うちらが聞いた話と同じみたいやね…信用してもええみたい」 一美は雅子に頷いてみせる。遠藤はベッドに寄り、横たわる人物に目を向けながら言う。 「学院長は、大変ご高齢でね。この学院を創立された方の、長女に当たられるんだが。目下のところ、北条寺の問題をもっとも憂慮しておられる。それというのも、北条寺が魔女に変身したのは、この学院の環境というか、構造が深く関わっているからなんだ。それについて、君たちに是非、話しておきたいことがあるとおっしゃってね」 一美は、興味深い面もちで、ベッドに歩み寄る。 「この学院の創立って、七十年くらい前って聞きましたけど…なら学院長先生って」 「そうだ、今年九十五歳になられる。耳も不自由だし、声もあまり大きくは出せない。君たち、もっとベッドに近寄ってくれたまえ…そうだ」 ベッドの脇に腰掛けんばかりに一美が立ち、その後ろに雅子が寄り添った。羽布団がもぞもぞと動き、細い指が、布団の端から覗く。白髪が見える。ウェーブの掛かった長い髪。いきなりそれが、ぐねぐねと動いた。まるで白蛇のように。布団がはねのけられ、上体をまっすぐ起こした人物の顔が、一美とまともに正対する。 「しまった!!」 一美の悲痛な叫びが部屋に響きわたった。
52 一美の視野には、ただ二つの凶悪な目が映っているだけだ。至近距離でまともに見てしまった凶眼の力に、一美の全身は激痛に痺れる。血液が沸騰し、内蔵が煮え、骨が腐っていく感覚… 髪を白蛇に変え、異様にきらめく瞳を持った美少女。北条寺美緒の変貌に、雅子は声も出ない。その横で一美が両手で頭を抱え、のけぞって絶叫した。魂も凍る絶望と恐怖の悲鳴だった。そして一美はそのまま、棒のように硬直して倒れる。頭が床板に激突して、血が流れた。 美緒の頭髪の蛇が、ゆっくりと黒くなり、普通の髪の毛に戻っていく。舌なめずりをして、ベッドから降り立ち、横たわる一美を見下ろす。まるでマネキン人形が倒れているみたいに、一美の姿は固く引き攣り、精気がない。遠藤がかがんで、一美のだらりと伸びた腕に触れ、手首を探った。 「死にかけているぞ…やりすぎじゃないか」 「かまわないわ。どうせ私の手下の獣たちに食わせてしまうつもりよ」 「一美さん!!」 ようやく、雅子の口から叫びが漏れる。一美にすがりつく。倒れた長身の少女は、ぴくりともしない。薔薇色だった頬は土気色に褪せ、半ば閉じられた瞼に瞳は隠れて、ただ白く濁った目。側頭部の傷からゆっくりと血が髪を濡らし、床に垂れて行く。 「どうして、どうしてこんな事を?!」 雅子は歯を食いしばり、美緒を振り仰ぐ。その凄まじい目の光りに、思わず遠藤がたじろいだが、美緒は静かに微笑した。 「説明する必要があるかなあ…雅子、あなたは、自分が食べる卵や肉や魚に、いちいち断りや謝罪をしてるかい?蟻をうっかり踏みつぶしたときや、顔に止まった蚊を潰すとき、何か説明してる?」 「一美さんや…あたしは、肉や蟻だって言いたいの?」 呆然と呟く雅子に答えず、美緒は遠藤に指示する。 「そののっぽのエスパー、さっさとあの地下室へ放り込みな。雅子はここで私が缶詰にするから」 遠藤は無表情に頷き、ベッドの下から、麻の布団袋らしいものを引きずり出すと、一美の身体に手を掛ける。 「一美に触らないで!!」 雅子は激高した。遠藤の手を払いのけ、一美をかばって覆い被さる。胸に触れた一美の身体が、あまりに冷たくなっているのに雅子の心は凍る。 「雅子…わがままを言うと、あんたもそうなるよ」 吐息といっしょに、美緒の言葉が雅子の首筋をなめた。そのとたんに雅子は身動きできなくなる。金縛りにあった小柄な身体を、やすやすと美緒が抱き上げる。閉じることもできない目で、雅子は一美が麻袋に詰め込まれていくのを見守るしかない。もはや一美は、屍体にしか見えなかった。遠藤が麻袋を肩に担ぎ、ドアを開ける。軋みながらそれが閉じたとき、雅子は声にならない絶叫を挙げた。 (助けて!誰か、…神様!)
53 ドアの外で、すべてを聞いていたかれんと礼子は、遠藤が近づいてくるのを知り、パニックに陥る。悲鳴を上げようとするかれんの口を包帯の手で押さえ、礼子は無我夢中で隣の部屋のドアを開けようとする。鍵が掛かっていませんように! 間一髪、転がり込んだ部屋は真っ暗闇だ。かれんと礼子の荒い息が嵐のようにこだまする。遠藤が廊下の板を軋ませて通り過ぎ、去っていく。 混乱と恐怖で、二人ともなにも言えないまま、数分が過ぎた。やっと礼子が闇の中で、かれんの肩を抱き、耳元に囁く。 「ひどいことになったね。でも、なんとかまぁを助けなくちゃ」 「一美さん…一美さんが死んじゃうなんて」 かれんが身体を震わせて涙を流し始める。その頬を礼子が軽く張った。 「泣いててどうなるの!?考えなきゃ、なにが出来るのか」 「先生に、先生に知らせようよ」 「あのエンドーガメが、美緒の手下だったんだよ、もう先生なんか、どいつも信用できない…」 礼子は細くドアを開けて様子を探る。漏れ入った光で、自分たちが雑多ながらくたを置いた物置部屋に逃げ込んだことを知る。学院長室のドアに張り付き、耳を澄ますがなにも聞こえない。全く、なにも。 「これじゃしかたがない、エンドーガメを追いかけよう」 遅すぎたかも知れないと思いながら、礼子はかれんを引っ張り、足音を偲ばせて学院長室から離れた。階段を降りながら、ふと窓に目をやったかれんが、声を挙げる。 「あそこに、遠藤先生が」 麻袋を重そうに担ぎ、落ち葉を踏みしめて行く姿が、針葉樹の下に見えた。管理棟の横にはヒマラヤ杉の森があり、その向こうは礼拝堂だ。夢中で礼子とかれんは、遠藤の後を追った。 礼拝堂の北側にたどり着いた遠藤は、ポケットから真鍮の古めかしい鍵を取り出す。苔と落ち葉に覆われた、一見ただの壁に見えるところに向かって、それを突き出す。 「あんなところに戸があったんだ」「地下室って言ってたよね」 かれんと礼子は、針葉樹の幹に身を隠し、息を殺して遠藤が出てくるのを待つ。
学院長室の窓からは、かれんと礼子の後ろ姿がよく見えた。美緒は、抱き寄せた雅子に頬ずりしながら、それを指し示す。 「あんたのお友達は、みんな可愛いね。そして可哀想だね。一美も礼子もかれんも、雅子の目の前で、むごたらしく死ぬんだ。ただ、雅子の友達だったという理由で」 雅子はほとんど放心状態になりながら、つぶやく。 「教えてよ…おねがいだから。どうして、あたしをいじめるの?あたしがなにをしたの?なんのためにこんなことを」 美緒は、限りなく優しく、そして残酷に雅子を抱きしめる。 「私だけが、雅子の友達に、ただ一人の友達になる…いいえ、雅子を所有する唯一の者になるためによ…雅子、私は、あなただけを愛しているの」 時がとまった部屋の中で、美緒は雅子を抱きしめ、うっとりと囁き続ける。
54 遠藤が立ち去った後、礼子とかれんは地下室の扉を開けようとしたが、どうすることもできない。礼子は決心する。 「職員室に乗り込んで、大勢の先生の前で堂々と言おう。地下室に一美が、学院長室にまぁが閉じこめられているって。こんな昼間に、いくら美緒だってそれを止めることなんてきない」 かれんの顔にも生気が蘇る。 「そうよね、大勢で行けばなんとかなるもんね」 二人は走った。管理棟一階の職員室。ドアを勢いよく開ける。大声を張り上げようと息を吸い込む。その礼子の顔が歪み、からだが固まる。 「こら、だめじゃないかあ。ドアを開ける前にはノック。名前とクラスを名乗って、用件を告げる。生徒手帳に書いてあるだろう」 いたずらっぽい笑顔で、二人の前に立っているのは遠藤だ。かれんが床にへたりこみ、礼子は後じさりする。自分たちが、敵の掌の中に囚われた無力な少女であることを二人は知った。
ここは夜の世界なのか…一美はぼんやりとそんなことを考える。周りがただ、闇だから。黴と腐った木の匂い。汚水が溜まっている気配も近くにある。淀んだ空気。どこかでこんな雰囲気を味わったっけ…小さい頃探検した、古墳の石室の中か…じゃあ、ここはお墓? 私は死んだのだろうか?そんな気もするが、どうも違うみたいだ。身体全体が痛くて寒くて耐えきれないほど不快だ。そんな感覚があることは、まだ身体と魂が切り離されていない証拠だろう。 ふと、一美は耳を澄ます。何か聞こえるような気がした。 「…これが運命というものだよ。わたしの遠い遥かな娘よ」 太く、温かく、湿った女の声。からだが震えるほど、懐かしい声。 「あんたは、誰やの?」振り絞って声を出した一美に、女は答える。 「無理に声に出さなくても、想うだけでわたしには聞こえるよ。愛おしい娘。わたしは大地の黒い母。ずっとこの闇の中に住んでいる。色々な名前で呼ばれてきたよ…ホルスの母イシス、アポロンの妹アルテミス、大地の母デメテール、泉のシベール、女禍、イザナミ、マリア、マドンナ…」 (黒い聖母?) 「ここでわたしを見た人間は、そう呼んだね。好きなように呼んでおくれ。それでわたしが変わるわけではないから」 (運命…私はどうなるの?ここで死ぬの?北条寺美緒に負けたまま) 「あのメデューサが、ここへあなたを放り込んだのが運命なのだよ。わたしはどんな子も許す。けっして死なせはしない。そしてあなたには役目があるのだよ」 (美緒を倒して、雅子を助けること?) 「いいえ…メデューサをこれ以上不幸にしないこと。メデューサがあの少女を目覚めさせることを防ぐこと」 (あの少女って…雅子のこと?目覚めさせる?どういうことなの?) 「雅子の意識の端は、闇の深淵につながっているの。メデューサはその闇の深さを侮っている。あの少女を魔女として目覚めさせて、その力を自分に取り込むつもりなの、あの不幸な蛇の子は」
55 「それが…美緒の意図やったんか!」 うめきながら、一美は力を振り絞って体を起こそうとする。激痛が背骨に走る。左手首と右足首が引っ張られる。一美は身体を反らされ、手錠で手足を繋がれていた。 「お待ち。無理をしてはいけない。むごいことをされたね」 闇の中で、温かい気配が動き、一美の身体を目に見えないなにかが覆う。痛みが和らいでいく。それと共に、一美には不思議な視力がついた。何の光もない地下室の様子が見え、さらに奥の壁の向こうに浮かんでいる、人のかたちの輪郭がとらえられるようになる。 (あなたは…壁の中にいるの?) 「土の中、大地の中なら、わたしはどこにでもいるわ。ただ、ここだけが、私が娘たちと話の出来る場所」 (あなたは…私のご先祖様なの?) 「あなたの一族の女たちも、メデューサも、メデューサに囚われている子も、みんなそうよ。わたしはみんな愛している。みんなに愛と食べ物を与えるの。さあ、わたしのお乳を飲みなさい、傷ついて飢えた子よ。」 一美の眼前に、たわわな乳房が光っている。その肌は黒檀の色だ。反射的に唇が開き、幼子そのままに、一美はその乳首を含む。熱い液体が、血のように熱い乳が、一美ののどを潤し、死にかけていた細胞を蘇らせる。一美は夢中で吸いながら、目を閉じた。涙が流れた。 (おかあさん…)
なにも考えることが出来ないまま、礼子はその日の授業を受けた。かれんも同じようだ。最後の時限が過ぎ、何の話題もなくホームルームが済み、級友たちはそそくさと教室を出て行く。だが礼子もかれんも、席を立つことが出来ない。 うちひしがれたまま、見つめ合っていた二人は、ふと気づく。宮前香奈が、やはり席に座ったまま彼らを見守っていること。担任の野木も、立ち去りかけて、戸口で振り向いたままじっとしていること。 「おまえたち…どうしたんだ?」 野木が、頼りない声で尋ねる。彼の顔は数日来憔悴し、精気がない。 「野木先生は、どこまで知ってるの?北条寺や、遠藤先生のたくらみ。まぁや一美がどんな目に遭っているか…」 礼子が、立ち上がって叫んだ。ほとんど捨て鉢な口調である。 「すまない…僕がまるで力不足で、教師としても、人間としても、なにもできないままで」 野木は肩を落とし、手で顔を覆う。香奈が立ち上がる。 「野木先生、もう、やめましょうよ、こんなこと。これ以上、美緒に脅されるままに黙っているなんて。もう沢山でしょう、うじうじしたまま、あたしを抱くだけの毎日なんて」 きっぱりと野木にそう言うと、香奈は礼子に顔を向ける。 「どこなの?花宮さんと鳴滝さんは。美緒も一緒?」 「香奈…」 礼子とかれんは、微かな希望を見出して、頬に血を通わせる。(続く)
56 温かな乳首から唇を放すと、一美は闇を見上げる。黒い聖母の顔は見えない。 (ありがとう、たったいま生まれた子供のように、私の中には力がみなぎっている) 「黒い美しい髪の娘よ。サヨコという娘がわたしに頼んだのよ。メデューサに殺された女の子を生き返らせて欲しいと。そのためにも、おまえの力が必要なのだよ」 (サヨコ…どこかで聞いたような気がする…) 「今、メデューサの虜になっている子が、いつか教えてくれるかも知れないね」 一美は頭を振り、身体に力を込める。手錠の鎖が軋む。念じた。 (手首と足首、鋼鉄になれ。筋肉、ヘラクレスやサムソンのように強くなれ) 激しく鎖がこすれて鳴った。高い音と共に、合金の環が弾け飛ぶ。手首と足首に残った手錠の残滓を、白く細い指が易々と引きちぎった。 起きあがった一美は、乱れた髪をなでる。側頭部の傷口に右手の人差し指で触れる。固まりかけた血を指先に付け、右目の縁に、ぐい、と赤黒い線を引き、目尻に太く長く伸ばす。左目にもそうする。それは、古代エジプト王女の化粧のようにも、蛮族の戦士のいくさの装いのようにも見えた。さらにハンカチを丸めて傷を押さえ、その上に真紅のバンダナで鉢巻きをした。 (一つだけ聞いていい?黒い聖母) 足を踏みしめて、しっかりと立ち、一美は壁の奥に目を凝らす。 (魔力を使いたい、魔女になりたいという美緒の願いを叶えたのも、あなたなの?) 声はためらわずに答えた。 「そのとおりよ。わたしは、娘たちの願いは、何でも叶えずにはいられない」
雲の切れ目から、奇蹟のように覗いた夕陽。それが今、黒い針葉樹の森の向こうに沈んでいく。 管理棟の階段を、二人の人影が手を繋いで降りる。ウエーブした髪を長く腰まで垂らした少女と、ボブカットの小柄な少女。不思議に静謐で絵のように美しい道行き。 美緒は、絶えることなく雅子に語り続ける。 「私の最初の記憶は、病院の天井。頭に包帯を巻かれて、ベッドに寝ていた三歳の夏。ママが私をモップで殴って、頭の骨が折れたの。でもそれが初めてじゃなかったんだって。私の頭、ずいぶんいびつなんだ。もっと小さい頃から何度も骨折して癒着を繰り返して、変形してるんだって」 「不思議な力を使えるようになったのは、でもそのせいだと思う。きっと脳味噌もかき回されて、普通と違う神経の繋がり方になったんだよね。チョウチョをおびき寄せたり、ピンポン玉を転がしたり、そうそう、スプーンを曲げたりしたっけ」 「ママとの楽しい想い出だって、あるよ。たまに、ひどく優しいときもあったんだ、ママって。そう、ピクニックに行ったなあ。小学校さぼれって言われて。ケンタのチキンの箱抱えて」 「ママが死んだのは、雨の日だった。増水した川に、私を突き落とそうとしたから、私、ママの脇の下から後ろに回って、ママの背中を押した」 「引き取ってくれたパパはいつも優しかったよ。欲しいものは何でも買ってくれたしね。でも初めてセックスさせられたときは痛かったな」 「私の髪が蛇に変わったのを見たときのパパの顔ったら、最高に笑えたなあ」 美しい声で、小鳥がさえずるように美緒は喋る。雅子の耳には、外国語の歌曲のように聞こえる。
57 逃げるようにみんな、学院から出ていく。生徒も教師も、職員も。誰に命じられたわけでもないが、本能が、このまがまがしい場所から離れろと告げているのだろう。クラブ活動をしている姿もまったくなくなった、午後七時。 幾つもの黒い影が、開け放たれた校門を通りすぎて学院に入る。警備員の姿はない。風ががらんとした校内を吹きすぎる。礼拝堂の高い尖塔と聳え立つ十字架が何かの光に浮かび上がる。 不意に礼拝堂の中のパイプオルガンが響きわたる。大バッハ作曲「G線上のアリア」 弾いているのはシスター福永だ。黒と灰色の修道女の服装をし、目を据えて鍵盤とペダル操作に熱中している。自ら奏でる妙なる音に身を任して、ただ無我の境地になろうと念じている。 ヒマラヤ杉の森の入り口に、雅子は立っていた。横には、美緒が微笑んでいる。二人の前に、異形の男たちが群がってきていた。汚れきったTシャツの上に革ベストを着て、金や銀の髪を逆立てた若い獣たち。それを率いる大男は、剃り上げた頭部に真っ赤なダリヤの花を入れ墨し、顔面を蝶の形をした鉄のマスクで覆っている。 「ホテイ、気に入った?その力」 美緒がにこにこして、ダリヤの入れ墨の大男に尋ねる。ホテイは、マスクから覗く口元をにやりとさせ、ベストのポケットから、百円硬貨を取り出すと、左右の親指と人差し指で摘み、牛乳瓶の蓋を破くように、ゆっくりと引きちぎった。 「最高だぜ。もっと早くこの力をくれてたら、ショウもあんな事にならなかったのによ。さあ、どんなことをすればいいんだ?ミオ」 ホテイの声は、期待に酔いしれている。 「まずは、この花宮雅子を好きなようにいたぶってくれればいいよ」 美緒は、楽しげに命じる。男たちはどよめく。 「犯(や)っちまっていいのかい?」 「なにをしてもいいよ。殺しさえしなければね。そのうち、面白いことが起きるよ」 礼拝堂から聞こえるオルガンの音が、さらに高らかに響く。アルビノーニ作曲「アダージョ」 「さあ、始めるよ!」
耳元でなにかが轟々と鳴っている。 それが、自分の吐く息の音だと、雅子は気付いていない。 全身に脂汗。ひっきりなしに木の根や石くれに躓いて、足は痺れて感覚がない。 彼女のいる木の下闇の底知れない深さ! 立ちはだかる木々は、どれも魔王のように巨大で、地面に付きそうなくらい下枝を垂らしている。そのとげとげしい黒いカーテンの中から、自分を狙う獣たちが次々と飛び出してくる。雅子は、涙を流し、腕を振り回して逃げ続ける。血走った目で、せわしく見まわす。礼拝堂はどこ!礼拝堂に逃げ込んで… パイプオルガンの響きを破って、不意に男の声が聞こえる。 「神は、お前など救ってはくれない。…『女は迷蒙、欺瞞、軽佻において男を凌駕し、肉体の弱さを悪魔と結託する事で補う。そして復讐を遂げる。妖術にすがって執念深き淫奔なる情欲を満たさんとする。奢覇都(サバト)は女たちの群れで埋め尽くされている―よもや魔女がいないとは言わせない』…そうだ、お前は…魔女に違いない!」 彼女は耳を押さえ、歯を食いしばる。激しく首を振る。 「違う!あたしは魔女なんかじゃない。美緒とは違う!」 「じゃあ、一美とも違うのか?」 雅子の脳裏に、誰かの言葉が蘇る。 (一美はあんたと同じじゃよ) その時、前方の、ひときわ巨大な針葉樹の根元に、巨大な獣が立ち上がった。両腕を広げ、雅子につかみかかってくる。雅子の身体は、疲労でもう動かない。目尻が裂けるほどに目を見張り、彼女はダリヤの花が突進してくるのを見る。 いきなり、ダリヤの花が真っ白になった。顔面に粉末消火器を浴びた大男・ホテイは、うめき声を上げてむちゃくちゃに腕を振り回す。雅子の視界に、礼子が飛び出してきた。 「まぁ!こっちだ、逃げよう」 消火器を抱えた野木が、迫る男たちを防いでいる。礼子は雅子の腕を掴んで走る。ヒマラヤ杉の森が切れる。雅子は目を見張った。(続く)
58 そこには、古ぼけたワンボックスカーが後部ドアを開いて待っていて、助手席から首を突き出しているのは唐沢由紀夫だ。緊張しきった顔で、雅子を見るなり叫ぶ。 「すぐに乗って!」 礼子に押されて後部座席に転がり込む。すでにかれんが乗っていて、抱きついて来る。 「野木先生!香奈!早く!」 礼子の悲鳴に近い叫びに、車のエンジン音が高鳴る。クラクションも響く。ハンドルを握っている男を見て雅子は驚く。由紀夫の父・多佳雄だ。いつもの茫洋とした雰囲気とは見違える精悍な表情である。 「まだ、まだ来ないの?」 かれんが地団駄を踏む。その時、森から二人の人影が飛び出す。野木は放射し尽くした消火器を、追っ手に向かって投げつけ、香奈の手を掴んで残った二つの席に飛び込んだ。同時にエンジンがうなった。ドアを閉めながら車はダッシュする。窓の外を、夕闇の桜並木が飛ぶ。校門が近づく。 「なんでユキが」 「まぁの携帯に入ってた番号、片っ端から掛けたの。そしたらこの探偵さんが」 雅子とかれんの叫びが交錯する。 「うん?誰か門に立っているぞ…」 多佳雄が顔を歪め、アクセルをゆるめる。礼子が身を乗り出す。フロントガラス越しに前を見て、目を飛び出しそうに瞼を開く。 「美緒!…止まっちゃ駄目!あいつを…轢いてもいいから!」 礼子の言葉に、由起夫が驚いて振り向く。 「そんな無茶な…」 かれんが身をよじって叫ぶ。 「無茶じゃないわ!あいつは人間じゃないの!お願い、行って!」 雅子は見た。美緒は、開いた門の空間に、なにも持たず、制服姿で立っていた。髪が風に揺れている。はかないほど美しい白い顔に、悲しげな表情を浮かべている。多佳雄が激しくクラクションを鳴らした。美緒は動かない。多佳雄は困惑しきって、ブレーキを踏む。 「止まっちゃ駄目!!」「行け!行って!!」 礼子とかれんが絶叫した。 どすん、と鈍い音が響き、ワンボックスカーは急に停車する。エンジンが回転を上げ、タイヤが空転する。多佳雄が喚いた。 「こんな…こんな馬鹿な!」 フロントガラスに、ダリヤの花が咲いている。花が動き、蝶の仮面が覗き、歯を剥いて笑っている口が見える。両肩の筋肉を盛り上がらせたホテイが、車を腕で押しとどめていた。 いきなり、フロントガラスに真っ白な蜘蛛の巣が展開する。ホテイが頭突きしたのだ。そして割れたガラスに腕が突っ込まれ、エンジンキーを回した。突然の静寂。 「これ…レンタカーなんだけどなあ。壊しちゃ困るよ」 多佳雄の間延びした声がやまないうちに、両サイドのガラスが叩き割られ、乱暴にドアが開き、瞬く間に車内の全員が引きずり出される。 「面白い事が起きるってほんとだったな。ミオ、どうすればいい?」 「男は殺し、女は犯す。単純でいいでしょ。雅子一人じゃ物足りないだろうし、人数は揃ったわ…そうだ、女がもう一人いたっけ」 「そうとも、ショウを痛めつけてくれた女エスパーを、渡して貰わなくちゃな」 雅子は茫然と美緒と大男の会話を聞く。反撃しようとした由起夫や野木が、革ベストの男たちにめちゃくちゃに殴られている。
59 また、ヒマラヤ杉の森の中へ連れて行かれた雅子は、礼拝堂の北側の壁が間近にあることを知る。そこに、遠藤が松明を掲げて立っていた。足元に何本も松明が転がっていて、次々と点火し、美緒のしもべたちに投げる。油煙を上げて燃える炎の環に、雅子と礼子、かれん、野木と香奈、そして由起夫と多佳雄が囲まれた。野木は半死半生で地面に投げ出され、香奈がすがりついている。由起夫も同じような状態で多佳雄が膝に抱きかかえている。ほとんど抵抗しなかったため、多佳雄はまだまともな状態だ。 「探偵さん…ピストルとか持ってないの?」 かれんが多佳雄に恨めしそうに言う。腫れた顔で多佳雄は頭を振る。 「お嬢さん、私は動物探し専門の探偵なんですよ。それにしてもこの人たちはいったい…」 雅子は、一人で立って、松明を持って囲む男たちを見回す。その瞳に炎が踊る。誰に言うともなく呟いている。 「なぜだろう…いつだったか、こんな光景を、あたし、見たような気がする…」 美緒の唇の端が、きゅっとねじあがった。遠藤に向かって頷いてみせる。遠藤は松明を掲げたまま、左手でポケットから鍵をとりだし、礼拝堂の壁に差し込む。 軋みながら開いたドアの中から、不吉な闇が流れ出す。遠藤は、若い獣たちに顎をしゃくった。 「中に、超能力を持った娘を転がしてある。たぶん、死んでいるだろうが、運んでこい」 死んでいる、という言葉に、礼子やかれんたちが凍り付く。松明を持った若者が二人、嬉々として地下室に降りていった。 「あたし…前にこんな経験をしたわ…火の棒を持った大勢の人に囲まれて、高い場所に立っていた。みんな、目をぎらぎらさせて叫んでいた…」 雅子が、夢見る表情で喋り続ける。礼子は立ち上がって雅子の肩を揺さぶった。 「まぁ!どうしたの!しっかりしてよ」 美緒が顔をほころばせて遠藤を見る。遠藤は複雑な表情で、どこか恐れるように雅子を見つめている。 その時、足音が地下室からあがってきた。重い足取りの若者が二人、松明だけを持って戸口に立つ。ホテイが苛立って叫んだ。 「なにやってんだおまえら、女エスパーはどこだ…」 ホテイの言葉が途切れた。ひきつった顔の若者の肩を、がしっと革靴が踏みつけ、しなやかな足が伸び上がり、長い髪をなびかせて、白いブラウスの少女が、暗黒の空めがけて翔けあがった。 「なんだと!?」「一美!!」 遠藤の驚愕の叫びと礼子の歓喜の声が炸裂する中、松明の炎に照らし出された一美は、ヒマラヤ杉の梢近くまで飛んでいる。左右に広げた両腕が、あおるように振られ、一美の顔の前で十文字に重なった。烈風が巻き起こって針葉樹の枝がちぎれ、無数の針の葉が、渦を巻いて舞い降りる。その渦の標的は美緒だ。 「ぎゃあああ!!…」 凄まじい悲鳴を上げ、美緒は顔を覆って身をよじる。超高速で落下した枝と葉は、美緒の全身をカッターのように切り裂いた。 降り注いだ枝葉の嵐と、巻きあがった地面の枯葉で、雅子たちには何も見えない。しかし美緒の悲鳴がうめき声に変わり、どさっと地面が鳴り、やがて葉っぱや埃も舞い落ちる。 遠藤が、ああ…と悲痛に叫び、肩を落とす。 針葉樹の葉に半ば覆われて、美緒は横たわっていた。着衣はずたずたになり、あらわになった肌は血塗れだ。腕や足が細かく震えているだけで、立ち上がる力もないようだ。 しかしほとんどの者は、美緒を見ていない。松明を手にした男たちも、肩を抱き合って震えるかれんや礼子たちも、視線はみんな上を見ている。 ゆっくりと、少女の身体が降下してくる。汚水に濡れたブレザーを脱ぎ捨て、ブラウス姿で、額に真紅のバンダナを巻いた一美。その全身は淡いグリーンの光に覆われ、なびく黒髪までも妖しい輝きを放っている。 「オーラだ!あたし、初めて見るよ」 かれんが感動の声を上げて、女神を仰ぐように手を握りしめる。 しかし、一美の顔は泣きそうだ。目には涙を溜め、がちがちと歯が鳴っているのを必死に食いしばり、自分が倒した相手の無惨な姿から視線をはずすことが出来ない。生まれて初めて「殺し」を経験した少女戦士は、泣き叫びたいのをこらえながら、地上に降り立った。
60 松明を持った男たちが一斉に後じさり、遠藤が一美を見つめて唇をわななかせる。 「どうして、どうやって復活した?」 ホテイが、激しく首を横に振り、空を仰いで吠える。 「うそだ!ミオがやられるなんて!」 目を輝かせて礼子が、一美に歩み寄り、笑顔で言う。 「すごい力だね、もう、怖いものなんかない。さあ、早くこんな気色悪いところから出よう!」 多佳雄が頷いて、由起夫を背負い、かれんの手を握って立ち上がる。香奈に支えられて野木も歩き出す。だが、雅子は夢見る瞳で一美を見つめているだけだ。 「まぁ…いったいどうしちゃったんだ?」 礼子のつぶやきも耳に入らない様子で、雅子はふらふらと一美に近づく。一美の涙に満ちた目に、恐れの色が浮かんだ。 「…魔女、だったんだね、一美さんも…あたしも?そうなの?」 雅子の顔には、不思議な笑みが湛えられている。全員がぎくりと足を止めた。その時、しゃがれた声が地面から湧き起こった。 「そうとも…そうだとも、私はずっとおまえを待っていた、雅子、早く正体を現せ、私のように」 かれんが、手を口に押し当て、絞り出すような悲鳴を上げる。針葉樹の葉をふるい落としながら、ゆらりと幽鬼のように立ち上がったのは美緒だ。ぼろ切れと化した衣服がそのからだから絶え間なく落ちていく。血だらけの裸体が剥き出しになる。それでも落下するものがやまない。かれんはもう、声も出ない。礼子がうめき声をあげた。 「皮が、美緒の皮膚が…!」 ずるずる、ぽろぽろと、美緒の全身から血にまみれた皮膚が剥け落ちていく。その下からは、輝くばかりに美しい少女の裸身が現れていく。 「私は不死の蛇さ。皮を脱いで何度でも蘇るんだよ」 顔の皮膚を払い落としながら、魔女が哄笑を噴き上げた。ホテイを始め、異形の男たちが歓喜の叫びを湧かせる。 「おれたちのミオは、不死身だ!」 全裸の美緒の、新しい皮膚は、虹のような光を放っている。爬虫類のような鱗、錦蛇のような斑紋が、透明な皮の下から瞬間的に浮き出ては明滅を繰り返す。くしゃくしゃだった髪がざわめき、波打ち始めた。一本一本の毛の先端が膨らみ、眼球と牙が光る。 遠藤が松明を振って、男たちに叫んだ。 「美緒を囲め!脱皮したばかりはまだ弱い、守るんだ」 既に猛然と一美は、美緒に突進していた。一撃でしとめきれなかった悔いに顔を歪ませつつ、瞳に闘志を燃やして、一直線に走る。 その前に立ちふさがった革ベストの男たちは、一美が触れる前に、念動力ではじき飛ばされて、地面に転がる。ナイフやチェーンや特殊警棒がむなしく宙を切り、誰一人一美の前進を止められない。 しかし、巨大な壁と化してホテイが立ちはだかった。拳をかざし、胸を張って一美に咆哮する。一美が怒鳴る。 「どきいや!!」 「骨までぐしゃぐしゃにしてやらあ!」 地響きを立ててホテイが一美に体当たりしてきた。瞬間、一美の姿が消失する。美緒が歯ぎしりした。 「テレポートしやがった!どこだ」 その美緒の頭上数メートルの空中に、一美が身を逆さまにして現れると、手刀にした右手を鋭く振った。細い手に押された空気が旋風となって叩き付ける。その空気の刃は剃刀の鋭さを持っていた。身を転がして、美緒はかろうじて直撃を避けたが、蛇と化した髪が数十本切れて飛び、地面に落ちる。のたうち回る蛇たち。 「よくもやったな!これを食らえ!」 呪詛と共に、美緒の頭髪が一本の大蛇のように伸びて、空中の一美を襲った。ハンマーで打たれたような衝撃を受け、一美の身体はくの字に折れて吹き飛んだ。
61 十数メートル跳ね飛ばされて大地に叩きつけられた一美は、よろめきつつ起き上がる。そこへホテイの巨体が戦車さながらに殺到してきた。 その時、多佳雄が信じられない素早さで、近くにいた男が持っている金属バットをもぎ取り、走るホテイめがけて投げつける。銀の光線となって飛んだバットは、巨人の足の間に絡まり、ホテイはもんどりうって前に倒れる。怒りに震えて美緒が多佳雄を睨み付ける。 「美緒の目を見るんやない!」 叫んだ一美は、そのまま踏み出そうとして、胸を押さえ、唇を噛み締める。美緒の髪に打たれた肋骨に激痛が走る。 多佳雄は、襲ってくる男たちをふわりふわりとかわしながら、長い手足で、冗談のような軽いパンチとキックを繰り出している。それが不思議なほどに的確に相手の急所にヒットして、三人が倒れた。しかし、後ろからバタフライナイフが襲って来た。 「危ない!」 礼子が悲鳴を上げながら、上段回し蹴りでナイフを叩き落す。間髪を入れず多佳雄のストレートパンチが相手の顎を捉えた。 美緒が、ゆっくりと一美に向かって進み始める。その肌の虹色の輝きは、目も眩むばかりだ。 「お前の限界はわかってるんだよ。無理をしない方がいい。諦めて私に雅子をよこしな」 一美は、あえぎながら、赤く縁取った目尻を吊り上げる。 「どうして…花宮でないとあかんのや?!」 雅子は、対決する二人を見守って、ただ茫然とたたずむ。しかし、その瞳に踊る炎は勢いを増している。 「まだそんなことを言ってるのか。雅子を飲み込めば、私は誰にも負けない力を得ることが出来るんだよ…それに、一美、おまえだって、雅子を狙ってこの学院にやってきたんじゃないか。おあいにくさま、こいつは私の獲物だ」 ざあああああ・・ 波のような音が湧きあがった。美緒の髪が一斉に一美に向かって伸び、千切れて地面に落ち、そのままくねって進んで行く。数え切れない毒蛇と化して、一美一人を狙って押し寄せて行く。 雅子が大きく目を見開いた。一美に向かって手を差し伸べる。毒蛇の群れに足を踏み入れて行く。 「一美が死んだら、あたしも!」 雅子の足に毒蛇が絡み付き牙を立てようとしていた。言葉にならない喚き声を上げて、一美が雅子に駆け寄る。両手で蛇を掴み潰し、放り投げ、足で蹴散らし、踏みにじる。毒の牙が一美の肌に突き立てられるが、鉄を噛んだように刺さらない。狂乱したような動作で、一美は毒蛇たちを殺戮し続ける。その姿を見て魔女が嘲う。 「みっともないダンス踊ってるみたいだよ、一美、おまえの力はそんなもんじゃないだろう」 「やかましい!この外道、地獄に堕ちいや!」 握りつぶした蛇の血で、どろどろになった拳を振り上げ、一美は絶叫する。美緒はさらに高く笑った。 「まだわかんないの?ここが、この世界が、最初から、地獄なんだよ」
62 礼拝堂のパイプオルガンは絶える事なく鳴り続けている。「G線上のアリア」から「アルビノーニ作曲「アダージョ ト短調」そしてパッヘルベル作曲「カノン ニ長調」へと。 壮麗な響きの中で、死闘は続く。すがり付いて来る雅子を左腕で抱え、一美は右手の手刀で、生き残った毒蛇たちの首を薙ぎ払う。蝮、鎖蛇、ハブ、ガラガラ蛇、ブラックマンバ、デスアダー、インドコブラ…首を絶たれ、胴を潰され、のたうつ忌まわしい鱗の波を乗り越えて一美は進む。抱きかかえていた雅子を、由紀夫に向かって押しやる。 「花宮を守って!」 鼻血で汚れた顔だが、由紀夫は強く頷いて雅子の肩に腕を回し、ヒマラヤ杉の根元へ退避する。 一美の全身から、オーラが高く立ち上った。グリーンの光は前傾し、美緒に向かって矢のように飛ぶ。美緒はうなり、眩しそうに顔を背けながら、掌で光を受ける。美緒の身体から、赤い光が滲み、一美のオーラを押し戻しながら膨れ上がる。 大気が震えた。緑と赤の光は一美と美緒の戦意そのままに噛み合い、激突する。不可視の力が真っ向からぶつかり、相手を圧倒しようとしていた。せめぎ合う光の先端から、電光がほとばしり、バリバリと空気を切り裂いて、きな臭い匂いが見守る者たちの鼻孔を突く。風が渦巻きながらヒマラヤ杉を叩き、枯葉を巻き上げて視界を奪う。礼子は腕で顔を覆いながら地面に伏せる。旋風の唸りがパイプオルガンの音色をちぎる。 一美は物体を動かすのでなく、念動力を直接美緒にぶつけて、魔女の肉体を破壊しようとしていた。美緒もまた、念動力で対抗している。拮抗が破れない。一美の額から汗が流れ落ち始めた。美緒は笑っている。虹色の肌は妖しい輝きを増すばかりだ。 「あっははああ!そうだ、気持ちいいよな、一美。こんな風に戦える奴を、私は待ってた。そうともさ、私とおまえは同類なんだ」 「ちゃうわ!!」 一美は唇を歪めて吐き捨て、右手の人差し指を高く差し上げた。暗黒の天から雷鳴が轟く。巨大な閃光が真昼のように森の中を照らした。耳をつんざく大音響と同時に天空から稲妻がくねって、礼拝堂の十字架にからみつき、針葉樹の枝葉を貫いて、地上の美緒を直撃した。 あまりの眩しさと凄まじい音に、誰も美緒がどうなったか見えない。しかし一美だけは茫然と立ちつくす。彼女には分かった。魔女は蛇の髪を網のように広げて雷電を受け止め、吸い込んだのだ。 静寂の中、オルガンが、バッハの「カンタータ147番 主よ、人の望みの喜びよ」を奏で始める。ずしり、と美緒が歩み出す。強烈な精気に溢れ、自信と凶暴な喜びに満ちて。 一美は荒い息を押さえられず、肩を上下させながら、後じさる。息を飲んでいたかれんが、不意に辺りを見回し、不審そうに呟いた。 「なんだろ…すごく良い香りがするよ。薔薇園に迷い込んだみたいな」 礼子が悲痛に顔をひきつらせた。 「いけない!一美は、超能力を使うと、脳細胞が壊されるんだって。この薔薇の香りは、その死んだ脳細胞の匂い…」 「そうさ、これは一美の死臭なのさ!」 美緒が笑いながら、髪を二本の鞭にして振った。瞬時に一美の両足首を捉える。倒されまいと踏ん張る一美の身体がのけぞり、宙に浮く。そのまま一美は、ヒマラヤ杉の幹に叩き付けられる。 念動力のバリアで身を包み、衝撃は和らげた。しかし、美緒の髪を引きちぎることが出来ない。振り回され引きずられ、一美の肌が傷つく。美緒はどんどん一美を引き寄せていく。魔女の額に、ひときわ巨大な蛇の頭が生えていた。鎌首をもたげたキングコブラ。開いた顎から長い牙が突き出し、先端に透明な液体が滴る。 両足を引きずられ、尻餅をついて身動きのとれない一美に向かって、キングコブラの扁平な頭が、ゆっくりと伸びていく。巨象も一噛みで倒す毒牙が一美ののどをめがけて飛んだ。
63 かれんと礼子、そして香奈が悲鳴を上げたその瞬間、一美は向かってくるキングコブラに逆に体当たりし、鎌首を両手でつかんで、美緒のところまでジャンプした。予想もしない動きに美緒の髪はもつれ、少女戦士と魔女は絡み合って転がる。枯葉と砂塵を巻き上げて戦う姿が、松明の明かりの中で激しく揺れ動いた。 動きが止まった。一美が上だ。しかし、美緒の蛇の髪に全身纏わり付かれ、締め付けられている。蛇たちは一美の腕に、足に、首に巻き付いた上に、至る所に牙を突き立てようとしていた。それでもその毒牙はすれすれのところで一美の肌に届かない。振り絞った念動力が阻止していた。 そして一美の両手は、蛇たちを一匹一匹掴み、美緒の頭からもぎ取り、引きちぎっては、投げ捨てていく。美緒が痛みと怒りに身悶えしている。 「そんなこと、いつまでもできると思ってるのか!」 一美の動きが止まり、少女戦士は喘ぐ。蛇たちの締め付ける力が倍加した。毒牙がじりじりと接近してくる。もう、一美は何もすることが出来ないのを悟った。その目が雅子に向けられる。 「雅子!礼子もかれんも、香奈も!みんな、離れるんや!走って!」 「一美、どうして…?」 礼子が叫ぶと、切れ切れの声が返ってくる。 「うちは…もう、力が、あらへん。最後の手を…使う。こいつの、身体の中に、瞬間移動、する。うちの身体と、こいつのが、分子、原子、のレベルで、ぶつかって、たぶん、爆発、する」 一美の言葉が理解されるまで、数秒掛かった。礼子たちの顔が蒼白になる。遠藤も美緒のしもべたちも愕然として立ちすくんだ。 美緒だけが、笑っている。 「やってみろ。水爆並みの爆発が起きるかもしれないし、私とおまえが混じり合って、もっと凄い魔女が誕生するかも知れないじゃないか」 一美もまた、凄絶に微笑した。 「そんなことには絶対ならへん。おまえとうちだけで、砕けるんや。」 「そうはさせない!!」 しわがれた声で叫んだのは遠藤だ。かれんに駆け寄り、抱きすくめて引きずり、美緒と一美の傍らに接近する。かれんはほとんど失神している。 「この子を巻き込むぞ。これで、自爆はできまい」 同時に遠藤は指で奇怪な印を組み、その喉から異様な発声が噴きあがった。 「イン・ゲ・トゥ・イ・ゲ・シ・サン・ミム・タ・シェ」 呪文の一音一音が、美緒に力を与えているようだ。魔女の裸身がぐねぐねと動いたかと思うと、手足までが蛇と化して、一美の胴と首に巻き付く。少女戦士はもう、声も出せない。「エロヒム、エサイム」「アラトオル、レピダトオル。テンタトオル。ソムニアトオル、ドゥクトオル、コメストオル、デヴォラトオル、セドゥクトオル」 呪文の進行と同時に、薔薇の香りが、さらに強烈に漂い始めた。 「終わりだ、一美。」 美緒が勝利を確信して告げた。 その時、雅子が由起夫を振り離して立ち上がり、絶叫した。 「そんなこと、許さない!!」
64 黒い旋風が森の中を駆け抜けた。松明の火があおられてことごとく消える。瞬時に暗黒となった空間、しかし、礼子は、数え切れないほどの人の気配を感じ、見回す。そして無数の青白い炎の玉が自分たちを取り囲んでいることに気づいて慄然とした。 その陰火に照らされて立つ雅子の瞳の中に、揺らめく炎がある。絶え間なく色を変えて燃え続けるそれは、何かの光を映しているのではない。彼女の内部で燃え上がる炎だ。 「ああ…思い出した。あの、西浜中学の北校舎…ユキと忍び込んだあの夜、校舎が燃えたのは…あたしが、火を付けたんだ!!」 細くうめく雅子自身が、この場にいる誰よりも混乱し、恐怖しているようだ。 「雅子…だめや、あかん、その火を、目覚めさせたら…雅子は」 絶え絶えに一美が声を振り絞る。美緒は一美の身体を締め上げながら、歓喜の笑みを浮かべた。 「やっと、やっとその時が来たようだね」 美緒の言葉に、雅子は激しくかぶりを振りながら、目をつぶって叫ぶ。 「一美さんを…あたしの・一美を・離して!!」 「これで、仕上げだ」 美緒が唇を歪めてせせら笑い、一群の毒蛇を雅子めがけて放った。 雅子の目が吊り上がり、美緒の凶眼に匹敵する視線が、闇を貫く。同時に雅子の足元から火の線が走った。毒蛇の群が、一瞬に炎に呑み込まれ、狂い回って灰になった。 雅子の前の、なにもない空間に、次々と炎が生じ、深紅の弾丸となって美緒に襲いかかっていく。美緒はうなり声を上げて一美を離し、火球を避けて転がる。雅子はまだ、力を制御できない。火球は美緒の動きに追従できず、あらぬ方向へ乱射される。 地面に倒れた一美は、朦朧とする視界の中で、雅子の泣き顔を見る。戸惑い、怖れ、怯えながら、雅子の中で何かが変わっていく。 「バガビ、ラカ、バガビ、ラマク、カヒ、アカバベ、カルレリオス、ラマク、ラメク、バカリアス」 遠藤が、声を張り上げて呪文を唱え始めた。耳慣れない発音の一つ一つが、闇の中に波動を広げる。火の攻撃に怯みかけていた美緒の顔に自信が戻る。 しかし、その時、森全体が揺らいだ。青白い火の玉の群れから、さざ波のように叫びが湧き起こる。 「私は」「もう」「我慢ができない」「あなたたちサヨコという」「媒体を使っているだけでは」「私はもう」 由起夫が蒼白になって立ち上がる。 「なんだ…サヨコの呼びかけ劇?!」 遠藤もまた、驚愕しつつ、必死の形相になって呪文を朗唱する。 「バラス、アロン、オツイノマス、バスケ」」 だが、姿の見えない数百の声が、遠藤の呪文に割って入る。 「もどかしい」「バノ、ツダン、ドナス」「私は」「やはり」「ゲヘアメル、クラ」「自分で」「オルレイ、ベレク」「話さなければならないと」「ヘ、パンタラス、タイ」「思い」「やはり」「決めた」「オ、イオ」「私は」「自分で」「六番目のサヨコに」「パン、オ」「なることに」「したのだ」「イアオ、イア」「そう」「私なのだ」 「私がサヨコなのだ」 「イア」「私は」「皆さんの前に」「アラディア」 「みんなのところに」 「やってきた」「イオ」「そう」「来た」「エボヘ」 「来た」「来た」「カルヌンノ」 「今」「イオ」 「ここに」「エボヘ」 「ここに」「ディアナ」 「ここに」「そう」 「ここに!」 遠藤の呪文を、ついに不思議な呼びかけが圧倒した。その瞬間、青白い炎の玉が、一斉に真紅の業火と化し、雪崩を打って美緒めがけて殺到した。 |
Copyright(c) 2003 龍3. All rights reserved.