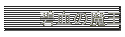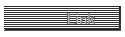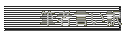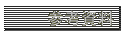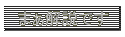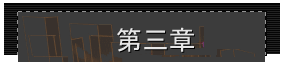
|
第3章・蛇たちの夜 |
|---|
|
33 誰もいない大きな建物は、空虚で無気味だ。しかし信仰を持つものなら、聖堂や礼拝堂を怖くは思わないだろう。そこには彼らの帰依する神がいるのだから。 一美は、波状に並ぶ黒ずんだ木のベンチに座る気になれず、礼拝堂の中を歩き回っている。正面の大きな十字架には、磔にされたキリスト。半裸の男の無惨な屍の像。その両脇には、聖人像が列をなし、少女の顔をした聖母マリアもいる。木像らしいその肌や手はあくまでも白い。 不意に、扉の開く音がして、人影が聖人像の列から湧きでた。十字架の背後にあたる位置には、いくつかの部屋が並んでいて、その一つから出てきたようだ。一美の知らない、中年の男性。 見上げるような背丈だが、禿頭で腹が出て、足も短く、あまり威圧感はない。目尻の下がった顔立ちに眼鏡をかけ、人の良さそうな雰囲気である。 「おや?君は授業中に、なぜここに?…シスターにでも叱られたかね」 男は笑顔である。一美はなんとなく笑みを返して、舌を出す。 「煙草を持ってるのを見つかってしもて、処分を待ってるんです」 「シスター福永だろう、犬みたいにすぐ嗅ぎつける…で、判決はどんなものかね」 「判決…裁判みたい。ま、停学一週間てとこやないかな。うちの経験で言うと」 「さあ…あまり前科を重ねてると、縛り首とか、火炙りとかになるかもしれんぞ」 男は愉快そうに、くっくっと笑い声をあげる。 「火炙りて…魔女裁判やあるまいし」 一美も笑い声をあげて、自分の言葉に、はっと息を飲む。魔女? 「そうだ、よく知っているね。異端審問にかけられ、魔女と判決が下ったら、火刑にされると決まっていた。その裁判の場所を、火刑法廷とも言った」 掌に汗が滲むのを感じつつ、一美は笑顔を保ったまま、尋ねる。 「あの…この学院の、先生、ですよね?うちは、一年D組の鳴滝いいますけど」 男は、一美の言葉にこたえず、あちこち指さしながら、歌うように言葉を続ける。 「君、知っているかね?この礼拝堂は実に面白い造りだし、その書庫には、興味深い本がコレクションされている。『Malleus Maleficarum』なんてものまであるんだから」 一美は、電撃を受けたようにびくりとする。…『魔女たちへの鉄槌』!!魔女狩り人どもの手引き書! 「…たとえ、魔女が人間を殺したり、害をなしたことなどなくても、人を治療し、嵐を退散させたりして益をなしても、生きながらの火刑に値するのだ。なぜなら神を捨て、魔王と取引しているから。想像しうるもっとも残酷な死に値するのだ…おっと、これは違う本だったな。一六世紀の悪魔学者、ジャン・ポダンの『悪魔憑きについて』の一節ではないか。」 一美の顔から笑顔が完全に消える。 「あなた…誰?」
34 男は、聖人像の前を行ったり来たりしながら、言葉に熱を込めて行く。 「なぜこんなに、悪魔や魔女、魔女狩りの資料が収集されているのか、私はずっと不審に思ってきた。この礼拝堂が、過剰なまでの魔除けの装飾に覆われていることも…それが、今になってようやくわかってきたよ」 男は、ひたと一美に視線を据えた。 「この学院は、『魔』を呼び寄せてしまう場所に建てられたんだ。おそらく、古代の宗教遺跡の上に、この礼拝堂が位置してしまった。そして創設初期に、おぞましい事件があったに違いない。そのために礼拝堂は改築され、悪魔払いの儀式をなすために本が集められた…なぜわかったかって?それは、いままた『魔』がこの地にうごめき始めたからだよ」 一美は、亜希のように人の心を読む能力が自分に備わっていないのを、痛切に口惜しく思った。この男の心がまったくわからない…そんな一美を見透かすかのように男は笑みを浮かべた。 「この学院には、誰にも手が付けられない『魔女』が育ちつつある。勇敢な花宮に期待してみたが、普通の人間にはとても…だが、君が現れた。魔女に対抗できる力を持った君が!」 「もう一度聞くで。あなた、誰!?」 一美の叫びが礼拝堂中に響いた。その反響のすさまじさに一美自身が耳を押さえて立ちすくむ。 「これは、失礼した…いや、君がちゃんと授業に出ていてくれれば、一昨日には顔を会わせていたはずだよ。私は古典を教えている、遠藤という」 男は、平然と言葉を継いだ。人なつこい笑顔が変わらない。一美は、戸惑いながら、遠藤の語ることに耳を傾けるしかなかった。 「さあ、君はその力で、あの花宮を救ってやらなければ…さもないと、花宮は、魔女の餌食となってしまうよ」 「遠藤…先生は、うちのなにを知ってるいうの?」 一美は、強い息苦しさを覚えて、うめくように言う。 「見たのさ…君が、なにもない空間から教室の入り口に現れ、そしてあの魔女に対抗して、普通の人間には持ち得ない力を発揮しようとしていたのを…私は味方だ、鳴滝一美。手を携えて、魔女を滅ぼすのだ」 遠藤は一美の間近に歩み寄り、かがみ込んで少女の瞳をのぞき込む。一美は遠藤の視線を避けた。心が動揺し、どう対応したらいいかわからない。 その時、大きく軋み音を立てて、礼拝堂の扉が開く。逆光の中に一人の少女が立っている。 「鳴滝さん、決まったよ、処分。明日、反省文を出しなさいって、担任の野木先生に。真面目に書けばそれで済むそうよ」 宮前香奈が、事務的な口調でそう伝達し、すぐに立ち去ろうとする。一美は叫んだ。 「花宮は、大丈夫やの?」 「今さっき帰った。お母さんが迎えに来て。…まぁ、あなたに伝えてって言ってた。今日はありがとう、明日も必ず会えるねって」 香奈が消えて、再び扉が閉まる。息苦しさが蘇り、一美は足早に出口に向かう。背後から遠藤の声が密やかに響いた。 「時間がないぞ。魔女は、間違いなくおまえの喉を食い破る機会をうかがっている」
35 何とか、最後の授業まで耐えられた。一美は終礼を終えると、わき目もふらず教室をあとにした。美緒の視線は、あまり感じられないが、クラスメイトたちの、好奇と畏怖の目が背中に突き刺さってくるのが痛い。 学校を出た一美は、麻田かれんの家に向かった。突然の訪問に、かれんの母は戸惑ったが、同級生と知ると大喜びで応接間に招き入れ、クッキーや紅茶を運んでくる。 「あの、かれんさんは?」 あまりの歓待に辟易しつつ、一美が尋ねると、かれんの母は笑顔を少しひきつらせる。 「少し、待っていらっしゃって。あの子…ずっと部屋から出てこないんです。でもお友達がみえられたと聞けば、きっと…」 かれんの母は、それきり戻ってこない。一美は十分間待って立ち上がった。廊下に出て耳を澄ます。二階からかれんの母の哀願する声が聞こえる。 「…お願い、かれん。出てきて一緒にお茶を飲んで…鍵を開けて、せめて顔だけでも見せてちょうだい。スナック菓子とペットボトルの飲み物ばかりじゃ、参ってしまうわあなた」 声のする方へ、一美は階段を昇る。遠慮の色もなく現れた長身の少女に、かれんの母が驚く。ミッフィやらキティやらのキャラクターで装飾されたかれんの部屋のドアを、一美の拳がノックする。 「麻田さん、うち、鳴滝や。話したいことがあって来たんや。花宮さんと北条寺美緒のことや。入ってええか?」 沈黙していた部屋の中で、人の気配が動いた。ドアが開き、ウサギのようにおどおどした目が覗いた。母親が顔を輝かせて、中に入ろうとすると、ドアがぴしゃりと閉まる。 「鳴滝さんだけ、入って!」 しわがれた、まるで老婆のような声が響いた。 一美は、部屋の異臭と凄まじい乱雑さにも、顔色を変えない。ベッドに座っているかれんを見つめる。おそらくこの二日間、着替えてもいないだろうくしゃくしゃのパジャマ。両耳の上で髪を束ねているゴムも外れ掛かって、髪型などと言うものはなくなっている。むくんだ顔。荒れた皮膚。ベッドの枕元には漫画雑誌とコミック単行本が十数冊ちらばっている。 「今日、花宮が倒れた。美緒のせいや」 一美の言葉に、かれんは手で口を押さえた。一美は、かれんに並んでベッドに座り、軽く肩を抱く。 「麻田は、花宮の親友やろ?花宮を助けよう。麻田の力が必要なんや。うちに、美緒の事、聞かせてくれへん?」 かれんは、びくついて、一美の表情を窺いつつ、かすれた声を出す。 「鳴滝さん…あたしを守ってくれる?考えるだけで怖いの。あれからずっと、とても学校に行く気がしないの。でもその理由をママにも話せなくて」 「好きな漫画読んで、部屋に籠もってたんやね?」 一美は優しくかれんを抱きしめた。 「うちが聞いたげるし、何でも話し。気い済むまで、いつまでだって聞いたげるで」 かれんは身を震わせ、一美に力一杯しがみついて泣き始めた。
36 日が暮れる前に家に戻らなければ。 沢渡礼子は、腕時計を見ようとして、ジョギングのピッチを落とした。手に巻いた包帯がほどけそうになって立ち止まる。コンビニのまぶしい店内照明が目に入る。のどの乾きに気づき、店に入った。冷蔵の棚からスポーツドリンクを取りだそうとして、落としそうになる。思わず小さな悲鳴を上げたが、ペットボトルは空中で、しなやかな手に受け止められた。 「すみません!…え?」 見事にキャッチしてくれた相手を見て、礼子は絶句する。真ん中でわけた長い髪をなびかせ、鳴滝一美は、ボトルを掴んだままレジに向かう。そして振り返って言った。 「これ、うちがおごるし、ちょっとつきあってくれへん?」 コンビニの向かいは、小さな児童公園だ。制服の一美と、スウェットスーツの礼子は、ぎこちなくブランコに腰をかけた。沈もうとする夕陽が、四月の終わりのぼやけた空に滲んでいる。 「…そう、かれんも、学校行けてないんだ…」 一美の話を、礼子は手にしたポカリスウェットの蓋を開けもせず聞いていた。 「あんたの悲鳴を、携帯で聞いてしもうてから、怖くて美緒とは一緒にいれないって」 「美緒?なんでかれんが彼女と?」 「あんたに怪我させたの、美緒やろ?どう考えても」 一美がそうきっぱりと言うと、礼子は顔を伏せる。 「全然、覚えてないんだ。思いだそうとすると、ひどい頭痛がするんだ」 「それは…思い出したくないんやろね、きっと」 そこで言葉がとぎれる。礼子は顔を上げて一美を見る。いつもの気丈さが失せて、頼りない幼子の表情になっている。一美は、空を見上げた。 「今日の午後、花宮が教室にいいひんかった…それだけで、1Dはひどいことになってるえ。あんなに花宮の力が大きかったなんて、うちにはわからへんかった…」 「まぁは、ちょっと見ると普通の子だけど、すごいポテンシャルがあるんだ」 礼子は、自慢するように呟く。一美はちらっと顔をほころばす。 「麻田と沢渡は、花宮のこと、身内みたいに誇りに思うてるんやね」 だが、礼子は笑わない。かぶりを振ってまた顔を伏せる。 「でも…まぁは、どこか壁を作ってるんだ。かれんは親友だって言ってるけど、まぁの方はそう思ってるだろうか?あたしは、なかなかまぁが本心を明かさないところがクールで気に入ってんだけど」 夕陽が海に落ちた。残照が空を染めている。 「時間がないんよ。うち、これから花宮のところにも行きたい。その前に、沢渡、あんたのあの晩の記憶を…知りたい」 一美が厳しい表情になる。
37 礼子はブランコから立ち上がり、よろけながら一美から離れた。 「いやだ。もう日が暮れちゃった。あたし、家に帰らなきゃ」 その時、ブランコの後ろ、ジャングルジムの天辺から声が降ってきた。 「ベイビー、これからがお楽しみの時間なんだぜ。そんなつれないこと、言っちゃ駄目じゃん」 若い男たちの嘲笑が、どっと礼子と一美を包んだ。一美は弾けるように、ブランコから降り立ち、唇を噛んで見回す。周りには、十人を越える人影が、卑しい笑い声を響かせていた。 「なに…このパンク野郎たち」 礼子があとじさって、一美に背中をぶつけてくる。残照を背にして、笑いながら間合いを詰めてくる男たちの影は、皆、頭部が醜怪な鬼のようだ。すぐに一美は気が付いた。グリスやクレイで固め、針や角みたいに尖らせた髪型でそう見えるのだ。服装もそれに見合ったものだった。汚れきったTシャツの上に、鎖の附いた革ベスト。鋲を打った首輪やリストバンド。ぼろぼろのジーンズには、髑髏やゴブリンのパッチ。 そして、彼らの身体の装飾!唇に安全ピンのピアスを刺している者。鼻や耳たぶに数え切れないピアスをぶら下げている者。剃り上げた頭にダリアの花を入れ墨している巨漢。両腕が蛇のタトゥーで埋まっている者。頬に白目を剥いたアンパンマンのワッペンを縫いつけている者。 「こんな千葉みたいなど田舎に、わざわざ来た甲斐があったぜ、グラビア飾れる美少女がふたり」「即いただきだ」「お嬢ちゃんたち…大人しくしててね。してても、怖い目に遭うんだけどね、残念ながら」「げははは…」「ぎゃひひひひ…」 一美は歯を食いしばる。一人でいたなら、どんな状況からも脱出できる自信がある。でも礼子を残しては、跳べない!仕方がない! ジャングルジムから、野獣の身のこなしで若い男が飛び降りてくる。際だって精気に満ち、凶暴な雰囲気も群を抜いていた。どう見ても彼がこの一団の首領だろう。逆立てた髪は虹色に染められ、両目の上から、削げた頬に向かって稲妻のタトゥーをしている。 酷薄な笑みを浮かべて、少女二人をねめまわしていたその首領は、怪訝そうに片方の眉を吊り上げる。礼子は唖然として、一美を振り返った。 「な、なにしてんの、こんな時に」 一美は、通学鞄から引っぱり出した大判の板チョコレートを、忙しく銀紙をめくってむさぼり食べている。 「怖くて頭おかしくなっちゃったのお?可哀想に」「そんなものより、もっと美味しい僕のチョコバーをしゃぶらせてあげるからあ」 男たちが歓声を上げるが、一美はわき目もふらず板チョコを食い尽くし、茶色に染まった唇をなめた。 「脳細胞に頑張ってもらわなあかんから、糖分が仰山いるんや」 「え?」 一美のつぶやきを理解しかねて、礼子が首を傾げた瞬間、一美は礼子の腕を掴み、まっすぐ前に突き進んだ。安全ピンピアスの男が、両腕を広げて抱きついてくる。 一美の腕から、通学鞄が風を切って飛び、安全ピンもろとも男の顔を叩きつぶす。悲鳴を上げた顔から、通学鞄は見えない糸に引かれるように、まっすぐ一美の手に戻った。 うなり声をあげ、ピアスをじゃらじゃら鳴らしながら襲ってくる男の手には、ヌンチャクがある。一美は鞄を振ってヌンチャクの一撃を、顔すれすれで払う。不自然に回転したヌンチャクは、ピアス男のこめかみを強打した。 「何だあ?この女?」 蛇のタトゥーをした手に、大型のサバイバルナイフが握られた。背中を丸め、一美の大腿部をめがけて突いてくる。再び鞄が飛んだ。重い鞄の直撃で、ナイフは吹き飛び、蛇のタトゥーは手首を骨折してのたうち回る。鞄は瞬時に一美の腕に戻っている。 空気を切り裂く音がして、頭にダリヤを彫った巨漢が、太い鎖を振り回し始めた。一美は間をおかず鞄を投げつけた。分厚い胸にめり込んだが、巨漢は倒れず、笑い声をあげて鎖を一美の足に叩き付ける。 一美はジャンプして鎖をよけた。そのからだが、そのまま平行に移動し、礼子を抱えて包囲の輪を突破する。 「逃げるんや、走って!」 礼子を突き飛ばすと、一美は振り返り、横殴りにしてきた特殊警棒を鞄で受ける。強烈な打撃によろめいた一美の足を、鎖が薙ぎ払った。
38 横転した一美は足首を抱えて顔を歪ませる。特殊警棒を握った少年が歓声を上げて一美の通学鞄を蹴飛ばす。巨漢が、舌なめずりをしてゆっくりと歩み寄る。 「手加減したんだぜ、足、折れてはいないだろ」 無造作に毛むくじゃらの腕を伸ばして、一美の肩を掴もうとする。 裂帛の気合いが宵闇を裂き、スウェットスーツの礼子が、一美を飛び越えて、巨漢に跳び蹴りを放った。顔面ど真ん中を捉え、鼻のひしゃげる音がした。吼え声をあげて顔を押さえる巨漢から、礼子は一美を引き離す。 「あかん!逃げろ言うたのに」 「だから一緒に逃げよ」 一美の肩を支えて走ろうとする礼子の前に、敵が回り込んだ。頬にアンパンマンのワッペンを縫いつけたそいつは、手に黒い箱を握っている。スタンガンだと礼子が気づいた時、一美が右手を伸ばし、掌を一杯に広げる。スタンガンがその手に接触して、まばゆい閃光が放たれた。火花は一美でなく、逆に男の身体に走り、アンパンマンのワッペンがちぎれ飛んだ。大きく開けた口から舌を突きだして、敵はのけぞる。 一美は倒れる相手を見向きもせず、右側から迫ってきた敵に、右手を槍のように突き出す。指先から電撃が走り、特殊警棒を振り上げた少年が、手足を痙攣させて地面に転がった。 「やるじゃねえか、姫が手強い相手だと言ってただけはある」 怯む男たちの中から、虹色の髪が進み出た。首領は、人差し指に何かを通して、くるくると回している。虹色に光る円盤…CDらしいが、中央の穴がやけに大きい。 首領は、何の気負いもなく、人差し指のCDを、すい!と宙に放った。銀色の光線となって一美の顔面に飛んでくる。身体をひねり、危うくかわした一美の頬に、一筋の血が浮かんだ。一美の顔が蒼白になる。 (CDの縁を研いで刃物にしてあるんだ!) 「ショウのチャクラムは、誰もよけられないぜ!」 男たちが勝利を確信してどよめく。ショウと呼ばれた首領は、両手にCDを掴み、同時に投げた。円形の軌道で、藍色の空に舞い上がる。螺旋を描いて高く昇っていく。笑顔でそれを見上げていたショウは、右手の親指を突きだし、ぐいと下を指した。2枚のCDが急降下を始めた。 (こいつ、念動力で武器を操ってる!) 驚愕しつつ、一美は棒立ちになっている礼子を抱きかかえ、地面に身を投げた。目に見えない猛スピードで落下したCDの一枚は一美の髪を数十本断ち切って舞い上がらせ、もう一枚は、ブレザーの背中を切り裂いた。 苦痛に耐えられず、うめき声を上げた一美に、礼子が悲鳴を上げて抱きつく。一美は、ショウが両手に再びCDを握っているのを見て、叫ぶ。 「礼子!離れて!!」
39 礼子は大きく弾き飛ばされて、ジャングルジムに背中をぶつけた。とりあえずの逃げ場と直感し、身をよじって鉄棒のジャングルに入り込む。 二枚のCD=チャクラムは、それぞれまったく別の動きで一美を狙う。左のは大きく旋回して後ろから襲って来た。右のは、蛇行しながら、一美の腹に突っ込んでくる。始めはゆっくり、一美に近づくに従って、見えないほどの速さで。左肘と、右前のポケット、ブレザーが再び裂かれた。しかし肌は傷ついていない。チャクラムはなぶるように一美の周りをゆっくりと旋回し始めた。 「着てるもんを全部ズタズタにして、ヌードを見ようぜ」 ショウが高らかに笑う。男たちが指笛を鳴らし、手を叩く。 一美の瞳に、強烈な輝きが宿った。礼子は、目を見開き、息を飲む。一美の全身から、陽炎のようなものが立ち上って見える。風が起こった。公園の砂やゴミが舞い上がり、一美の周りに渦を巻く。小さな竜巻に包まれた一美の髪が、炎のようになびき、逆立つ。 「奴のシナプシスの電気信号…周波数…わかった!」 一美が目を細め、呟いた。 とたんに、チャクラムの動きが乱れ、中空に張り付く。ショウの笑いが消え、顔に汗が噴き出す。 「な、なんだとお…おれのチャクラムを、止めやがった。…分捕る気か!」 浮かぶチャクラムが、釣り針に掛かった魚のように、めちゃくちゃに暴れ始めた。ショウが歯を食いしばり、一美も頬を紅潮させて、見えない綱引きをしている二人の間の空間が緊迫する。チャクラムの動きが、再び止まっていく。ショウの顔面は、脂汗でびしょぬれだ。 「てめえら、ぼさっとしてんな!援護しろ!」 ショウが悲鳴に近い声を上げた。凍り付いていた男たちが、まごつきながら武器を構える。金髪の双子の少年が、バタフライナイフを振り回して、一美を左右から挟み撃ちにしようと迫る。 轟!と竜巻が弾けた。膨れ上がった旋風が空中のチャクラムを奪い、一美がのばした右手人差し指の上に運んだ。金髪の双子は恐怖して後退した。 ショウの下顎が、がく、と開いた。唇から涎を流し、白目を剥いて膝を突くと、前のめりに地響き立てて倒れる。 「ボスは負けたで。まだ、やるんか?」 涼しい顔をした少女が、二枚のチャクラムを、お手玉のように上下させると、男たちの顔に怯えがくっきりと浮かんだ。 公園の隅の方から、けたたましい犬の吠え声が湧き起こる。逞しいシェパードが、中年女性の持つ引き綱をちぎりそうに猛って近づいてきていた。遠くからパトカーのサイレンが聞こえる。一美が、微笑を浮かべ、浮いていたチャクラムを指ではじいた。ふわふわと男たちに向かって滑り出す。悲鳴を上げて、傷ついた者も含め、異形の若者たちは全員逃走を始めた。
40 一美は、倒れているショウに近づき、かがみ込んで言う。 「おまえら、誰に頼まれてん?」 やっとのことで首を動かし、ショウはひきつった顔を持ち上げる。 「おれの、姫さ。名前は…ここに彫ってあるぜ」 ショウが指さした顔の右側を見て、一美は口に手を当てる。吐きそうになる。 男の右の耳たぶは、ちぎったようになくなっている。残った穴の周りに、M、I、Oと半円形に入れ墨がある。 「へへ…この耳は、姫に捧げたんだ。おれ自身で切り取って、姫に食べてもらった。そのご褒美に、チャクラムを操る力をもらったのに…畜生」 「たかがCD舞わせるしょぼい念動力…その耳、犬に食わせた方がまだよかったわ」 冷たく一美が言うと、ショウはがっくりと顔を伏せた。もう見向きもせず、一美は歩き始める。通学鞄を拾い、吠えるのをやめて尻尾を振り始めたシェパードの前を通り過ぎ、礼子を振り返る。 「はよ行こ。パトさんが来る前に」
住宅街を足早に行く一美に、礼子はやっと追いついた。声を掛けようとして、場違いな香りに気が付いた。甘く漂う、薔薇の花の芳香。それは、一美の身体から痕を引いているようだ。 「なにこれ?香水?さっきまで付けてなかったのに」 礼子の言葉に一美は立ち止まり、はっと鼻に手をやる。強く唇を噛みしめる。身体がぐらっと揺れた。 「大丈夫!?」 礼子が支えようとする手を押さえ、一美は、礼子の顔に、ふっと息をかける。目眩がするほど強く薔薇が匂った。驚く礼子に、一美は静かに話しかける。 「あんなあ、これ、うちが『力』つこうた代償なんよ。脳のグリア質が燃えて、崩壊して立てる匂いなんや」 「ちからって…超能力!」 礼子が叫ぶと、一美は唇に人差し指を当て、寂しそうな笑顔になった。 「世間的にはそう呼ばれてるよね。つかいとうはなかったけど、今日はしかたあらへん」 「脳が燃えるって…なんともないの?」 「脳細胞の四割までは壊れてもなんとかなるらしいけど…な」 青ざめた顔に、気丈な表情を浮かべると、一美はまた歩き出す。 「花宮の家には…バスに乗るんやったね…面倒や、タクシー使お」 足を運ぶ一美の上半身が、変にこわばっている。礼子は思い出した、一美の背中は…
41 (聖アガタ女子学院教諭・某の覚え書き・その1) 私が、「ノワール」を受け継いだときからの不文律の一つが、「いっさい文書を残さない。何一つ記録を取らない」ということだったが、今、それを破る。なぜなら、かつてない事態が進行し、あるいは最悪の結末が訪れるかも知れないからだ。後始末をする人間が、誰か必要となるかもしれない。この文章がその誰かの助けになってほしい。 そもそも、この学院が「処女(おとめ)らが清く正しく聡明に過ごす学舎」であったことなど、創立以来一瞬もなかっただろう。問題を起こす人間は、生徒にも教職員にも絶えず居た。学院の名誉を守るために、闇に葬らなければならない事件は、ひっきりなしだった。非行、窃盗、不倫、横領、堕胎、傷害や殺人まで…それを処理するための専門家が生まれ、いつしか「ノワール」の称号が冠された。汚れた仕事をあくまで冷徹に遂行する影の存在。 すべき事は不祥事を学内にも世間にも知らせず解決するという一点。生徒を傷つけて放逐することもあった。父兄を脅し、あるいは金で懐柔して口を塞いだ。学院の腐臭を嗅いでつきまとってきた記者を抹殺(社会的に、あるいは直接的に)した。それだけ我が手を汚し、苦心惨憺しても何の報酬もない。誰も賞賛や慰労の言葉を与えてはくれない。ただ、自分の力で学院を守っているという誇りだけが、ノワールの黒き栄光。 七年前、ノワールとなった私には、その使命感と誇りがあった。この任務を受け継ぐ事が出来るのは自分をおいてないと自負していたし、何も知らない教師たちはもちろん、校長や学院長をも支配下に置いている優越感が私を満たしていた。 だが、二年前、Mを「補導」することになってから、ノワールは甚だしい変質を強いられた。学院の暗部で公に出来ない仕事を遂行するという本来の任務から本質的な逸脱を始めたのだ。 Mへの「補導」の中身は、ありふれた…一番ありふれたものだった…それが、あの少女の一言が私を震撼させた。Mは黒き栄光を奪った。あれから、ノワールは、私は、Mのしもべだ。 ノワール…黒きもの。私はMに出会って、真の意味で暗黒の世界の住人と化したのである…
42 雅子の部屋。蒼白な一美と礼子、そして涙ぐむ雅子がいる。玄関では暗くて見えなかったが、二人とも膝をすりむき、衣服のあちこちに砂が附いている。雅子は一美のブレザーに触れた。三カ所の裂け目があり、背中は… 「血が滲んでるよ!ひどい傷…」雅子の手が震える。 「まぁ、早く手当してやって!」礼子が小さく叫ぶ。 「手当って…救急箱しかないよ。病院に行かなきゃ」 「病院は、あかんの。消毒して絆創膏貼るだけでええ」 きっぱりと一美が言い、ブレザーを脱ごうとして、顔を歪める。慌てて雅子は脱ぐのを手伝う。一美のブラウスの背中は真っ赤だ。 勉強机の椅子に横に座り、一美はブラウスをとる。髪を上に上げて、うなじから肩、背中が剥き出しになる。優美としか言いようのない滑らかなからだの線と、艶麗な肌の輝き。しかし、首の根本から肩胛骨の下まで走る傷が無惨だ。幸い深くは切れていない。出血はほとんど止まっている。血を拭い、消毒し、絆創膏で傷を何カ所も止めて開かないようにする。その上から包帯も巻き付けた。雅子と礼子が汗を滲ませて治療する間、一美は一言も声を出さずに耐えた。 「ブラウス、あたしのじゃ、サイズきついから、ママのを借りたよ。制服もこれじゃ着れないから…兄貴のブルゾン」 「おおきに」 一美は素直にブラウスの袖を通し、ブルゾンを羽織る。ふう、と礼子が息を付き、カーペットに置かれたクッションに腰を落とした。雅子はベッドに座った。 「どうしてそんな怪我を、礼子も膝が傷ついてるよ」 「こんなのなんでもない、それより…」
礼子と一美は、交互に公園での死闘を話した。聞き終えた雅子は、じっと一美の顔を見つめる。一美はその視線を受け止めて、笑っているような、泣いているような表情を浮かべた。 「簡単に信じてもらえるような話とちゃうよね」 雅子は激しく頭を横に振った。 「ううん!一美さんが、礼子が、嘘なんかつくはずない。その傷がなによりの証拠だし」 「信じるの?うちが、『超能力』つこうたいうことも?」 一美の声は恐ろしく真剣だ。雅子はまっすぐ一美の目を見つめて、静かに頷いた。一美の表情が、微かに動揺する。 「まあ…ええか。このことが済んだら、うちは転校せなあかんやろし、そうなったら、うちのことは、すぐに忘れてな」 半ば、捨て鉢の口調で、一美が呟く。雅子は立ち上がった。顔色が変わっている。 「どうして?どうして転校しなきゃならないの?嫌だよ、あたし、そんなの!」 「なんでて…うちが、こんな力持ってることを、礼子や花宮に知られてしもたからや。昼間のことで、クラスのみんなも、薄々気づいてるやろし…気色悪いやろ。こんなんが、側にいると」 雅子の勢いに圧倒されながら、一美は自嘲の歪んだ笑みを浮かべる。雅子は怒りに頬を紅潮させた。 「ちっとも気色悪くなんかないよ!一美さんは、その力であたしや礼子を救ってくれた!何にも悪いことしてない!みんなと、ちょっとだけ変わった個性を持ってる、それだけのことじゃない!あたしが一美を守るよ!絶対、転校なんてしちゃだめだよ!」」 地団駄を踏み、手を振り回して叫ぶ雅子の頬に、涙がこぼれている。 「まあ…ちょっとだけっつうのは無理で、かなり変わってるとは思うけど…あたしも、感謝してる。一美は、正義のジャンヌダルクみたいだよ。気色悪いのは美緒のほうだ」 礼子が、雅子と一美を見比べながら、とりなすように頷いた。 一美は、雅子の涙を見つめている。身じろぎもせず… 一美が激しくまばたきをする。そして、小さく唇が動いた。かすれたささやきが漏れた。 「ありがとう…」
43 雅子と一美が黙って見つめ合っているのに照れたように、礼子が声を上げる。 「とにかく、みんなで力を合わせて、やっていこ」 頷いた雅子が、話を継ぐ。 「あたし、今日、保健室でね、香奈と話したんだ。香奈は美緒のこと、色々教えてくれた。野木先生も美緒に操られてるんだって香奈は思ってる。香奈も美緒にがんじがらめにされてる。シスター福永の陰にも、美緒がいるんだって」 一美が雅子に身を乗り出す。 「うち、美緒のことをなんにも知らへん。香奈の話、もっと聞かせてや」 「うん。あのね」 その時、勉強机の上でジムノペディの着信音が鳴った。 「はい…あ、かれん?!元気になった?」 携帯電話を耳に当てる雅子の顔に、笑みが広がる。 「そう、一美さんが話を聞いてくれて…えへ、あのね、今、一美さん、この部屋にいるんだよ」 とたんに、かれんの声が、一美や礼子に届くほど大きくなった。 「行く!今すぐあたしも行く!ねえ今夜、まぁのうちでみんなでお泊まりしようよ!」 一美が激しく首を振った。 「それはやめたほうがええよ。夜、一人で外出するのは、もう危なすぎる。うちらを襲ったような奴らが、かれんを待ち伏せしてるかもしれへん」 雅子が事情を伝えると、かれんの声はすっかりおとなしくなった。 「じゃ、明日学校でね」 雅子が電話を切る。 「じゃあ、できるだけ香奈の話したとおりに喋るよ」
…私、中一の時から、いじめてたのよ。美緒を。いじけて暗い顔してたから、あのころの美緒。良い気晴らしだったわ、勉強しすぎていらいらしたときなんか。それが、春休みが終わって、中二の新学期になったら、まるで人が違ってた。誰も美緒をいじめるなんて出来なくなった。先生たちまで、怖がるようになった。 …噂よ、もう誰も口にしなくなった、噂だけど…美緒、黒い聖母に会ったんだって。そして魔力を授かったって。 …私は他のことも知ってる。美緒は中一の終わりの春休みに、産婦人科病院に行ってるの。塾に行く途中で偶然見かけたのよ。そこって、すごく簡単に、妊娠中絶引き受けてくれるって噂なの。 …私、春休みが明けて始業式の日に、美緒をそのことでからかったの。そうしたら、美緒、笑ったのよ、ものすごくおかしそうに。いきなり、私に、突きつけたの。首からペンダントみたいに提げてた、あれを! …真っ赤な毛糸に通した、勾玉(まがたま)だったわ。そう、弥生時代の人が身につけてたアクセサリー。でもそれは、古代の遺物じゃなかったの。美緒は言ったわ。 「これは、あたしの赤ちゃん。無理矢理堕ろされちゃったあたしの分身。全部はもらえなかった。ちっちゃな血の固まりみたいなものしかあたしには抱かせてもらえなかった。あたしはそれを粘土と混ぜて、この形にして、焼いたの。一生、この子と一緒にいるためにね」って。 …笑おうとしたのよ、私も。でも怖かった。美緒がもう、いじけた弱虫の女の子じゃなくて、私が想像もできない人間になってることがわかったから。
44 (聖アガタ女子学院教諭・某の覚え書き・その2) Mは、私に言ったのだ。堕ろした赤ん坊を、抱かせてくれと。どんな形になっていてもかまわないからと。死にものぐるいの勢いが私を圧倒した。私は、I医師からそれをもらいうけて彼女に渡した。Mは、それを陶土とこねて勾玉にし、オーブントースターで焼き固めて身につけた。 それ以前からMの目は、特異な光を放っていたのだが、顔つきと雰囲気が目に見えて変わったのはそれからだ。誰もが驚くような美貌の少女に変身し、少女ファッション雑誌の読者モデルに選ばれた。モデルクラブや芸能事務所に出入りする一方で、学院内や他校の不良生徒には女王のように君臨し始めた。 ノワールとして私はMの変貌の様子を探り、驚愕した。彼女は極めて未熟ではあるが、いわゆる超能力を発揮し始めていたのである。自分の髪の毛を自由に動かし、それを蛇であるかのような幻覚を、相手に起こさせることで、どんな不良をも怯えさせ、配下にしていた。 それは私の世界認識をも一変させる発見だった。私は、かねてから学院内で大量の魔女や悪魔払いの文書、そして魔術書そのものが所蔵されている事に気づき、研究していたのだが、あくまで趣味的な探求に過ぎなかったそれらを、現実に使用できるかもしれないと思い至った。 Mは私の申し入れを、待ちかまえていたようだった。 忘れもしない、あの金曜の深夜、私はMを礼拝堂北側、通称「黒い聖母の森」に導き入れ、魔法陣を描いて、悪魔召喚の儀式をおこなった。 Mはその身の魔力を顕在化させ、正真の魔女に変身を遂げた。それは紛れもない事実である。 私は彼女と盟約を交わした。魔法使いと魔女として、お互いの欲望のために同盟を結んだ。私は彼女に知識と助言を与える。その代償としてMは学内の秩序維持に協力する。 最初は、興奮と喜びの日々だった。私は魔法書の呪文が現実に効力があることを彼女を通じて検証する事が出来て、学問の意欲を満足させていた。しかし、やがてMの破壊的行動が私を浸食する。 芸能関係者やアウトロー人脈と交際を始めたMは、麻薬や覚醒剤をこの地方都市に蔓延させ始めた。さらには、私が連れていった産婦人科医を、胎児や胎盤を商品として売りさばく闇のネットワークに繋ぎ、巨額の利益を彼女自身が吸い上げるようになっていたのである。 「先生、これから妊娠しちゃった生徒がいたら、いいお金になるよ」 天使の笑顔でそう告げたMに、彼女がもはや私の管理できない怪物と育ったことを悟らされた。 もう後戻りは出来なかった。かろうじてMは現在に至るも、学内にはドラッグを持ち込んだりはしていない。クラスで自らの支配力を示すだけで満足しているように見えた。だがその実、細かい工作をして、ほとんどの教師の弱みを握り、父親には巨額の寄付金を供出させ、不可侵の存在と化していったのである。
45 礼子が、そそけだった顔で首を振る。 「なんか、ソーゼツだね」 「美緒の家のことも、香奈はかなり知ってた。北条寺って何代も続く大きな地主の家で、東京にたくさんビルを持ってるんだって。でも美緒は小さい頃、お母さんと二人だけで苦しい生活をしてて、小学校高学年で、美緒だけ北条寺家に引き取られたらしいの。家族はお父さんとおばあさんだけで…」 そこまで雅子が話したとき、礼子の表情が微妙に変わる。敏感に一美がそれを察する。 「なにか、思い出したん?」 一美と雅子が見つめる前で、礼子は顔を歪め、唇を丸く開いて、舌を突き出した。手で慌てて口を押さえる。ぐうっとのどが鳴る。 「礼子!?」「こらえたらあかん!吐いてしまえばええんや!」 雅子と一美の叫びが交錯し、礼子の手の下から、逆流した胃液があふれ出した。駆け寄った雅子が礼子の背中をさする。反対側で一美も礼子の肩を抱き、がたがた震える礼子に密着する。 「さあ、頑張って、なにがあったか、逃げずに見るんや!」
…耳元でなにかが轟々と鳴っている。 それが、自分の吐く息の音だと、礼子が気付くまで、恐ろしく時間がかかった。 全身に脂汗。ひっきりなしに木の根や石くれに躓いて、足は痺れて感覚がない。 昼間なのに、なんて暗い場所! 仰げば針葉樹のはざまから、空は見えるけれど、青黒いばかりで光はない。 そして、彼女のいる木の下闇の底知れない深さ! 立ちはだかる木々は、どれも魔王のように巨大で、地面に付きそうなくらい下枝を垂らしている。そのとげとげしい黒いカーテンの中から、あいつはきっと自分を狙っている。 礼子は血走った目で、せわしく見まわす。礼拝堂はどこ! その時、彼女の目は、とらえた。 前方の、ひときわ巨大な針葉樹の根元に、それがいるのを。 目尻が裂けるほどに目を見張り、礼子は絶叫する。 それは…北条寺美緒の顔をした、メデューサ。頭髪が無数の蛇で、一目見ただけで人間は石と化してしまう魔物。 礼子は恐怖が自分を破壊してしまいそうなことを直感した。それを避けるには、頭を空っぽにして行動するしかない。習い覚えた空手の動きにすべてをゆだねた。拳を固め、恐怖の中心に突進する。身が凍るほど美しい美緒の顔、渦巻く蛇に飾られた美少女の顔面に、力一杯突きを打ち込む。連打する。 激痛が両腕を痺れさせた。目の前にあるのは、針葉樹の太い幹だ。血にまみれた拳を震わせて礼子は棒立ちになる。力の限り幹を殴っただけだったのだ。 耳元に、生臭い息がかかる。しゅうしゅうと、鱗のこすれる音。喉に、頬に、肩に這いずってくる、無数の蛇。 礼子の視界は暗黒に閉ざされた。
46 (聖アガタ女子学院教諭・某の覚え書き・その3) Mが級友や教師を怯えさせたり、非行や犯罪に関わっていくのは、最初、無目的で何の意味もないものに見えた。私が魔法書の実験を行うのに協力するのも、単に好奇心からのように振る舞っていた。 だが、彼女ははなから、無自覚に意図していたのかも知れない。すべてはMが魔女として強大化するための行動だった。悪意や憎悪や嫉妬、嗜虐心、ありとあらゆる人間の負のエネルギーこそ、彼女の魔を成長させる栄養となったのである。若い人間に無軌道に生命力を発散させ、それを吸い取ることも不可欠だったようだ。私が魔法書の呪文を唱える度に、Mは魔女としての階梯を密かに駆け昇っていたらしい。 そして、彼女の意図していることが、私にも次第に見えてきた。 彼女は、この世界が根本的に、間違って作られたものだと考えている。自分の悲惨きわまりなかった境遇は、この世界の歪みからきたものであると結論づけている。だから彼女は、この世界を滅ぼすことを希求し、それによってのみ自分は、本来いるべき場所に戻れると考えているのだった。 あまりにも途方もない考えだ。だが、行為の破廉恥さ反人間的な度合いと同じくらい、彼女の決意と意志は真剣きわまりない。私は問いかけた。 「世界を滅ぼすなどと言うことが、どうやったら可能なのだ?」 Mは魅惑的な笑みを浮かべて答えた。 「割と簡単だと思う。もう少しセクシーな魅力に磨きをかけて、米軍の核ミサイル将校を誘惑して、発射スイッチ押させてしまうとか。あ、ロシアの方が簡単そう。ローマ法王の脳を乗っ取って、イスラム教徒皆殺しの十字軍を起こさせるとかも面白い。手っ取り早い方法なら、原子力発電所の職員を手なづけて原子炉を暴走させるだけでも、地球に穴を開けられるんじゃない」 笑えなかった。今の彼女の力で、それは充分出来そうな気がする。 「どうしてすぐにやらんのだ?」 私が、息を詰めながら質問すると、Mは笑うのをやめた。 「邪魔しようとする奴らがいるからよ。そいつらが手を出せないほど、私が強く大きくならないと。もっと力を付けないと。もっと素晴らしい生け贄を呑み込まないと」 素晴らしい生け贄…私にはなにを指しているかわかった。Mが今、執着しているあの少女。少し小柄な、えくぼが愛らしい、この春編入したばかりの生徒。
47 悪寒に全身震え、えづきながら、礼子は喋り続けた。 「毎晩犯しに来る父親をぶちのめし、威張り散らす祖母を老人ボケにして、学校では誰にも馬鹿にさせない…そんな力を得るために、美緒はこの学院にいた魔法使いに頼んで、魔女にしてもらったんだって…」 すべて吐き出し終わった礼子は、ぐったりとベッドに崩れ落ちる。両方から彼女を支えていた一美と雅子が、礼子の顔に流れる冷たい汗と涙と胃液を丁寧に拭ってやる。 「よく、頑張らはったね、礼子」 優しい言葉に、礼子は一美を見上げる。 「負けないよね、一美は、美緒にも勝てるよね?」 「うん」 一美は深く頷くが、微妙に礼子と視線を逸らしている。どことなく無理に笑顔を見せる。 「うちらだけとちゃうしね。美緒と戦うのに味方になってくれる言う先生に、今日会うたよ」 「誰?そんな頼もしい人、うちの学校にいたっけ?」 雅子が首を傾げる。 「古典の遠藤先生、言うてた」 一美の返事に、雅子と礼子は顔を見合わせ、意外そうに驚く。 「うっそー、あのイケてないエンドーガメが?」 「なんやの?えんどーがめって」 「のっそりしてて、眼鏡が爺さんぽくて、ゾウガメみたいなんだもん」 「でも、授業じゃ陰陽師のこととか、オカルトチックな話もするんで、安倍晴明マニアの子にはウケてるよね」 少女らしいお喋りが飛び交い始めたとき、部屋の外から、雅子の母親が呼んだ。 「雅子、お友達といっしょに、降りていらっしゃい。お迎えが来られたのよ」 驚いて三人は部屋を出た。玄関に立っている人物を見て、雅子と一美があっと声を上げる。雅子の母とにこやかに会話しているのは、和服姿の成瀬奈津だ。 「おばあちゃん、なんでここが?」 「一美、こんなに遅くまでお邪魔してては、こちらにご迷惑でしょう。そちらのお嬢様もおうちまで送りますから、ごいっしょに帰りましょう」 表には、黒塗りの大型乗用車が、静かなアイドリングの音を立てている。運転席には髪を短く刈った、鋭い顔の若い女性が、パンツスーツ姿でハンドルを握っている。 奈津と共に、一美と礼子は後部座席に乗り込んだ。三人が並んでもゆったりと座れる。雅子はサンダルを突っかけて見送りに出た。窓が開いて一美が顔を覗かせる。髪が夜風になびく。湿って温かい空気が満ちている。 「じゃあ、明日、学校でね」雅子が思いを込めて言うと、一美が頷く。 「あ、反省文、忘れずに書いてくるんだよ!」 動き始めた車に、二・三歩小走りについて雅子が叫ぶと、一美は、しまった忘れていた、と慌て顔になり、すぐに、顔をほころばせた。この夜初めて見せた、心からの笑顔だった。
48 礼子を送り、その後ろ姿がマンションの入り口に消えるのを見届けた一美は、車に戻る。 動き出した車の窓に雨粒がぶつかる。ワイパーが動き始めた。 「あれ?家に戻るんと違うの?」 一美が奈津を振り返る。老女は前を向いたまま、無表情に呟いた。 「本当に無茶をする子ですねあなたは…傷の手当をきちんとして貰いに行くのです」 一族の一人が開業医をしている品川まで、東京湾を渡るらしい。一美はシートに斜めにもたれて顔をしかめた。 「そんな大した怪我やないのに…」 「あなたは一族の未来を託す大切な一人なのです。乙女の肌に傷跡を残すなんて許しませんよ」 奈津の目は厳しく光っている。一美は奈津のこの視線が苦手だ。いつもは優しい老女が、一族全体のことに関しては、非情で厳格な指導者の顔になる。視線を逸らし、一美はふてくされて呟く。 「亜希姉さんが知らせたんやな。でも、こうなることはわかってて、うちを転校させたんやろ、おじいちゃんもおばあちゃんも」 「わかっていたら…通わせはしません。こんな危険な試練になるなんて…あんな強敵が待っていたなんて。今からでも、他の学校に移れるものならと、わたくしは思っていますよ」 奈津の意外な言葉に、一美は少し動揺しつつ、反発する。 「もう転校は嫌や。それに、敵…だけやなかったよ、待っていたんは。うち、大切な友達も、見つけられたよ。初めて、普通の子に友達ができそうなんや」 「花宮雅子さんのことですね…まだ一美はわかっていないのです…」 奈津の瞳に、苛烈な閃光が走ったように、一美には見えた。 「わたくしたちは、誰でも一度は、普通の人と心の絆を結びたいと願い、でも、必ず裏切られるのです。危機の時に、普通の人間たちはわたくしたちの力を求めます。聖女や英雄と褒めそやしながら…。でも、それが過ぎれば、また彼らはわたくしたちを、魔女や怪物と呼んで忌み嫌う、その繰り返しだったのです」 「花宮も…うちを忌み嫌うときが来るいうの?」 一美の表情は、さらに動揺を深くする。奈津は、無表情を変えない。 「それと、いいこと?今度のことに、一族の支援を期待してはなりませんよ。今は誰も手一杯で、あなたの戦いは手伝えないのですから」 一美は唇を固く結んで頷く。 「わかってる。これは、うちの試練やし、避けられない戦いなんや。亜希姉さんが刺繍で予知したみたいに、うちは悪龍を倒す戦士になる」 車は海を渡る橋にかかり、スピードを上げる。雨に霞む波頭を見つめるうち、一美はしばしまどろんだ。
49 雨粒が窓ガラスを伝っている。ほとんど闇に近い部屋。微かな照明に浮かび上がる横顔は、濡れてくしゃくしゃの髪を頬に張り付かせた、北条寺美緒。 細く白い手が、携帯電話を握る。緑色の光が点滅する。 「…どうした?なにかあったのか?」 電話から男の声が返ってくる。美緒は陶然と、窓の外、暗黒の夜空を見つめながら、赤い唇を開く。 「こんな、なまあったかい雨の夜には、どうしたって思い出すんだよ。いつもこんな夜だった。私が初めて人を殺したのは。初めて男に抱かれたのは。初めて魔力を使ったのは」 「…おい、どこにいるんだ。滅多なところでそんな言葉を使うな」 「もう、いいのさ。もうすぐ、大いなる悦びの夜が来る。もう私は、隠れる必要がなくなるのよ」 「…もうすぐ?いつだ?いつ!」 「あんたも、本の中に埋まっていないで、外を見な。空気を嗅ぎ、このぬるい雨に打たれてみなよ。私の蛇たちが、暴れたくてうずうずし始めてる。古い木の根っこに埋められた死体たちが、早くさまよい出たいって呟いてる。川底に流された赤ん坊たちの骨が、岸辺に浮かび始めてるよ。もう、まもなくだ。私の魔力が最大になる祝祭の夜は」 「…どうしても、やるのか、花宮雅子を」 「そう、あいつを、永遠に私の物にしてやる、準備を頼んだよ」 「…待て、花宮はいいとして、鳴滝一美はどうする?絶対に邪魔をしに来るぞ、あの超能力を持った娘は、あなどれない」 「さっき、ショウのチームを仕掛けてみた。あいつらじゃ、歯が立たなかったけど、一美の力の限界もわかった。私の敵じゃない」 そう言い切って美緒は、また、夢見る表情でガラス越しに雨空を見上げる。 「前は、こんな雨の夜には、ベッドに潜ってふるえてたよ。あんたに魔女にして貰ってからは、もう悪い夢を恐れることもない。私自身が、悪夢そのものになったからね。でもそれも終わる。私の悪夢を世界にぶつけて、全部をぶっこわすその日も、遠くない」 絶句したらしく、男の声はもう聞こえない。美緒は、なおも楽しげに語り続ける。 「雨の音って、大好きだ。きっとママのおなかの中で聞いてた音に近いんだろうね…」 |
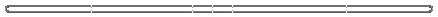
Copyright(c) 2003 龍3. All rights reserved.