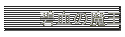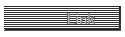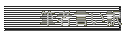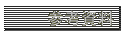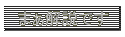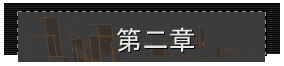
|
第2章・凶眼 |
|---|
|
17 残酷な夜が明けた。雅子は一睡もせずに朝を迎えた。制服を着てダイニングルームに現れた雅子の顔色を見て、母親は強く休めと勧めたが、雅子は首を横に振る 登校した教室にはまだ、誰もいない。自分の席に座り、机に頬杖を突いて、雅子は礼子とかれんの席を眺める。二人とも今日は欠席するとわかっている。 礼子は救急車で病院に運ばれ、そのまま入院した。指の骨折と、顔面の軽い打撲。そして…部分的な記憶喪失。なぜ彼女は自分が礼拝堂の裏の森に行ったか、そこで何が起きたのか、全く覚えていないのだった。 かれんは熱を出して自宅で床に就いている。礼子の救出を雅子から伝えられても、怯えはなかなか癒されないようだ。 悪夢のような夜を振り返りながら、雅子は気になる光景を想い出す。救急車に運び込まれる礼子を、学院にいた教職員が総出で見守っていた。そこから離れた校舎の陰から、野木が救急車を見ていて、その傍らには宮前香奈が青い顔をして立ちすくんでいた… 不意に、教室のドアが開く。反射的に顔を向けた雅子の目に、野木が映る。夕べは視線が合っただけで、一言も雅子とは会話を交わしていない。 「花宮…顔色が悪いな。今日は休んだ方がいいんじゃないか」 いつもは独断的で押しつけがましい口調の野木だが、今日に限ってその声には思いやりがある。雅子は意外に思って担任教師を見上げる。野木もまた、雅子に劣らず憔悴した表情で、髪もぼさぼさだ。 「野木先生こそ、顔を洗ってきた方がいいですよ。そんな髭面、ファンの子たちががっかりするわ」 野木は雅子の言葉を無視して、机の前に立ち、いきなり雅子の耳元に口を寄せた。 「頼みがある。夕べ、宮前と私が一緒に校内に残っていた事を、誰にも言わないで欲しい」 雅子は、弾けるように顔を反らし、脂の浮いた男性教師の顔をまじまじと見つめた。野木の表情は、ただひたむきに懇願していた。
18 いつもは私語でざわざわしている1年D組の教室が、静まり返っている。 「よしよし、こういう風に授業をやりたいと思っていたんだよ」 一時限の地理担当・小太りの青木は、そうはしゃいでみせたが、目を伏せて沈黙を続けている生徒たちの不気味さに、額に汗を浮かべて黒板に向かう。 静けさの中に緊張がみなぎっていた。ぽっかりと空いた二つの席。沢渡礼子と麻田かれんの居た場所が、ブラックホールとなって少女たちの活気を吸い込んでしまったようである。 板書することに閉じこもってしまった青木から目を背け、雅子は、ゆっくりと後ろに顔を向ける。その行動は全生徒の注目を引いた。教室中の視線を集めながら、雅子は北条寺美緒を見つめる。 机の上に腕を組み、その腕に頬を当てて、美緒は瞳を閉じていた。優雅にウエーブした髪がふわりと広がっている。その表情は、獲物をたらふく腹に納めて満足しきった雌ライオンのようだ。 不意に、美緒の髪が揺れた。不快そうに眉が寄り、美緒は目を開けて顔を持ち上げる。同時に、ドアが鳴って、長身の少女が姿を現した。 「一美さん!」 雅子は思わず立ち上がっていた。 「遅刻かい?見慣れない顔だねえ。あ!君か?転校生の鳴滝くんだね」 青木の言葉に、無言で頷いた鳴滝一美は、立っている雅子と一瞬瞳を合わせたが、素知らぬ顔で教室を見渡し、礼子の空席を見定めると、ためらいなくそこに足を運んだ。 慌てて雅子は着席する。生徒の全員が、一美と美緒を、固唾を飲んで見守る。 美緒は、無言ですうっと微笑んだ。次の瞬間、かっと目を見開き、すさまじい眼光を一美の背中に浴びせる。 その時、一美の左手が不思議な動きをした。人差し指と小指を立てて拳を握ったのだ。雅子は何の意味があるのかと戸惑ったが、効果は絶大だった。美緒が目に見えてたじろぎ、歯を食いしばって、一美の背から視線をそらしたのである。
19 休み時間になるのを待ちかねて、雅子は一美に駆け寄った。見上げる一美の表情は穏やかで険がない。 「よかった!一美さん登校してくれて」 「花宮さんの友達、二人も欠席なんやね。どないしたん?」 回りが異様に静まり返る。雅子は無理に平静を装い、一美を促した。 「うん…ちょっと、外出て話そうよ」 体育館横に、妙な石造りのモニュメントがある。幾つかの大小の石が苔に覆われていて、なにかの建物の跡かもしれない。教室や職員室からは死角の位置で、いつもひと気がなかった。雅子は石の一つに腰を下ろし、顔を両手でこすった。 「あたし、ひどい顔してるでしょ。昨夜ね…礼子が怪我をして…」
説明を聴き終わった一美は、大きく息をつくと、雅子の向かいに立ったまま空を仰いで、まぶしそうに目を細めた。 「それって…あの凶眼の持ち主の、仕業なんやろね」 「きょうがん?…美緒のこと?」 一美は、さっきのように、人差し指と小指を立てた拳を作り、雅子に示す。 「凶悪な眼…妖術の一種で、視線をぶつける事で相手に災厄や死をもたらすんや。この手は、それを弾き返す魔除けの印(いん)なんよ」 雅子は瞬きを繰り返し、しばらく言葉が出ない。一美は空を見たままで話し続ける。 「花宮さん、あんた、これから、薄うでええから、アイシャドーと口紅、塗りや。メソポタミア時代に始まったあのお化粧は、魔除けだったんや。邪眼や凶眼の力が眼や口から入り込むんを防いでくれるねん」 「その、手のサインじゃだめなの?」 「これは、『角(つの)握り』言うんやけど、多分花宮さんがやらはっても、効かへん。美緒の眼の力、昨日より強くなってたし、明日はもっと…」 淡々と語る一美の言葉を遮り、雅子は叫ぶ様に尋ねる。 「どういうことなの?美緒がそんな魔力みたいな力で礼子を傷つけたっていうの?そんな事を知ってる一美さんは…どういう人なの?」 一美は、痛みを感じた様に顔をしかめると背中を向けた。 「うち、今日は疲れた。やっぱりあんな椅子に座ってられへんわ。帰るし」 そう言ったまま、さっさと歩き出す。 「待って一美さん!」 追い掛けようとした雅子に、一美は足を止めずに顔だけで振り向くと、肩越しに何かを軽く投げて寄越す。反射的に受け止めた雅子が掌の中を見ると、それは真新しい口紅だった。 「塗っときや、教室に戻る前に」(続く)
20 放課後、雅子は担任の野木と一緒に、礼子の入院した病院を訪れた。こういう場合いつも付いてくる宮前香奈が、なぜか来ない。 礼子は、もう個室でなく大部屋にいて、となりのOLらしい患者と笑って話すほどに回復していた。雅子たちにも、笑顔を見せる。 「骨折って言ってもヒビが入っただけだって。空手やってるとこんなこと、よくあるんだ。パパなんて、試合でローキック浴びて膝のお皿割られても、気付かずに勝っちゃった事あったんだよ」 両手を包帯で覆い、顔もバンソウコウだらけだが、礼子は明るく、はしゃいでさえ見せた。しかし、昨夜何を経験したかについては、一言も喋らなかった。そして、雅子とはついに視線をあわさなかった。 その足でかれんの家を訪ねたが、玄関で母親と立ち話をしただけで戻ることになった。 「かれんはまだ目を覚まさないんですの。でも大丈夫だとお医者様は…かれん、毎日まぁさんの事ばっかり話してるんですよ。可愛くて、頭が良くて、真面目でリーダーシップがあってって。本当にその通りのお嬢さんね。これからもかれんと仲良くしてやってくださいね」 かれんの母は、くどいほどに雅子に頭を下げた。無垢な幼女がそのまま伸びやかに育ったと言う雰囲気は、母娘共に共通していて、顔立ちもそっくりである。 バス停に向かって歩きながら、雅子は野木に尋ねた。 「先生、鳴滝一美さんの住所、わかります?」 「ああ、クラスのみんなの住所電話番号は全部これに入れて持ち歩いてるが…」 野木はポケットの携帯電話を指し示した。 「今日、一時限だけ、出てきたそうだな、彼女。…これから行くつもりか?」 「ええ。」 「そうか…僕は、学院に戻らなきゃならないから」 バス停に着き、一美の住所電話番号を雅子に伝えたあと、野木はまだ何か言いたそうにしている。 「…?先生、あたし、ここから一美さんとこまで、歩いていきますから」 「ああ、じゃあ…」 残念そうに見送る野木に、雅子は振り向いて、首を傾げた。 「野木先生…香奈は、大丈夫ですよね」 「…すまん。そのうち、ちゃんと話す。まだ黙っていてくれ」 バスが来て、野木は唇を噛んで乗り込む。雅子は決然と歩き出す。その唇には薄く赤いルージュが引かれている。
21 成瀬家のチャイムを押すと、和服の柔和な顔の老婦人が現れた。おそらく七〇歳近いだろうが、結い上げた髪もつやがあり、若々しい。 「まあ、一美のお友達…あいにく一美は留守ですが、ぜひあがってくださいませな」 老女の笑顔があまりに魅力的で、雅子は断ることが出来なかった。 「あの、一美さんのおばあさまですね?」 「わたくしのこと?成瀬奈津と申しますのよ。ええ、一美はおばあちゃんと言ってくれますが…そうねえ、あの子の祖母の従姉のまた従姉というところかしら」 応接間に通され、茶の支度をすると言って奈津は去った。雅子はソファの座り心地の良さに驚く。部屋の調度はどれも年代を経て輝きを増している逸品ぞろいだ。 「花宮さん、こちらにいらしてくださいませな。主人がお話ししたいと申しております」 振り向くと、奈津が神妙な表情をして招いている。ふわり、と雅子は立ち上がった。何かこの老婦人には、抗いがたいものを感じる。 居間には、車椅子に身を沈めた小さな老人が待っていた。痩せた顔に、溢れんばかりの笑顔。その目は一美に似て、強い光を放っている。 「成瀬不二彦と申しますじゃ。お嬢さん…そうか、聖アガタで一美を待っていたのは、あんたじゃったか」 奈津が去り、二人だけになった部屋で、雅子は眉をひそめる。老人はかまわずに言葉を続ける。 「わしは、占い師なんぞという、胡散臭い商売をやっておる爺じゃ。じゃが、あの学校に一美の運命を変える者がおることは、確実にわかっておったよ。それにしても…」 不二彦老人は、しげしげと雅子の目を覗き込む。 「深い…深いのう。あんたの瞳は、恐ろしく底が深い。一美の光を全部吸い込んでしまうかもしれん。」 「あの…よくわからないお話ですが、一美さんのこと、お聞きしてよろしいですか?」 気おされるのに、必死に抗いながら、雅子は不二彦老人に言う。 「一美さんが、学校に出て来たがらないのは、あたしたちと違う、特別の力を持った人間だからですか?」 老人は目を見開き、大きく首を横に振る。 「お嬢さん、一美は、あんたと同じじゃよ」
22 夕暮れの校庭。どこかの中学校らしい。 野球部員が練習を終えて、片づけをしている反対側は、やや雑草が生え放題になりかけているが、丁寧に植えられた草花に囲まれて、一つの碑が立っている。 夕陽に染まったその碑の陰から、不意に小さな人影が立ち上がった。夕焼けよりも赤い色の服を着た、幼い女の子だ。ひどく怯えた顔をしている。唇が歪み、黒い瞳から涙があふれ出す。耐えられないように泣きじゃくって駆け出し、あっというまに姿を消す。 長い長い影を引いて、十代半ばと思われる少女が、碑の前にやってきた。革靴が、地面の花々を踏みにじり、蹴散らす。どの花も、瞬く間に無惨に萎れて行く。 「友情…か」 碑に手を掛けて文面を詠むと、少女はウエーブした髪を揺すって、高く笑った。澄んだ声の哄笑が空に駆け上がる。 瞬間、少女の髪が、独立した生き物を思わせる動きで、ねじれて鞭のように伸びると、碑に巻きついてギリギリと締め上げた。 こもった爆発のような音。同時に響く、幼女の絶叫。 友情の碑は、粉塵をあげて砕け散った。
23 海を見下ろす高台の家。アトリエから長い砂浜が見える。 一美は眩しい夕陽から目をそらし、振り向いてこの家の主人・亜希を見つめる。 二十五歳という年令より、ずっと少女じみて見える亜希は、刺繍作家だ。いつ訪ねてもこの大きなガラス窓に囲まれた、空に浮かんだようなアトリエで、色とりどりの糸を手にしている。その傍らに座り、じっと時を過ごすのが一美は好きだ。 亜希は生まれたときから耳が聞こえない。けれど彼女と意志を通じ合わせるのは、一美にとって、声を使うよりもたやすい。 (ねえ亜希姉さん、姉さんは学校に行きたかった?) 一美は、そう思いを発してみる。すぐさま答えが、直に心に返ってくる。 (ええ、とても行きたかったわ。友達とお喋りしたり、運動会や遠足…私の永遠の憧れ) 透き通るように白い肌、赤みがかった細い髪、亜希の容姿は妖精のようにはかなげである。生まれたときからほとんど家の外に出ずに育ち、絵画や手芸に親しんで過ごしてきた。読書量も半端ではなく、画集や図鑑、事典をはじめとする書籍で家の壁は埋め尽くされている。 (でも私は怠け者で意気地なしだったから、外《そと》の人たちと交際するのは無理だったのよ) 一美は、残酷な質問をしたと後悔する。念話(テレパシー)に優れている亜希は、聴力がなくても手話や読唇が必要ではない。しかし、それでは一般人と会話は出来なかった。加えて、大勢の思念が狭い空間で渦巻く教室で、悪意や嫉妬や憎悪などを直接感じてしまう亜希は耐えられるはずがないのだった。 (あなたが自分を悪く思うことはないのよ。あなたを通じて、私は女子高校の生活を今、味わってるんだから。私のためにも、もっと学校に行ってね) 亜希はそう笑って、刺繍糸を針に通そうとする。 しかし、その指が震え、膝の上から刺繍枠が落ちた。異常な緊張と恐怖が亜希から伝わってきて、思わず一美は側に駆け寄る。 「亜希姉さん!」 (ひどい!今、小さな女の子が、蛇に殺された!) 顔を覆って倒れた亜希を支え、一美は彼女をソファに運んだ。怯えて心を閉ざしてしまっているが、体調に深刻な変化はないようだ。どこか遠くの世界の出来事を、亜希は察知してしまったのだろう。 そう思って、一美は亜希に温かい飲み物でも作ろうと扉に向かった。足元に、亜希の刺繍枠が落ちている。何気なく拾い上げ、刺繍面に目をやって、亜希は立ちすくんだ。 そこには、毒々しい龍と戦う、白い鎧の天使が縫われようとしていた。そして、その天使の顔は…一美だった。
24 一美の保護者・成瀬不二彦と要領を得ない会話をして、家に戻った雅子はひどく疲れていた。 夕食を摂り、宿題に取りかかろうとする。でも集中できなかった。占い師だという成瀬老人の不可解な言葉、奈津の微笑、不思議な雰囲気の成瀬家…、一美には結局会えなかった。あの老人が、一美を聖アガタ女子学院に転校させたのか?それも、私に会わせるために?…色々な考えが頭の中に渦巻くうち、雅子は強烈な睡魔に襲われ、机に伏していた。
…(誰かが、悲痛な声を上げている。泣き叫んでいる。誰だろう?傷つけられた礼子だろうか?怯えきったかれんだろうか?…ちがう。もっと親しいけれど、遠くに行ってしまった誰か…霧の向こうから声が聞こえる。 足元はひどい雑草が繁っていて、素足をひどく傷つける。あたし、裸足で歩いてるの? 霧が晴れて、長い髪の女の人が見えてきた…あたしと同じくらいの女の子だ。あのセーラー服は、西浜中学? 地面に膝を突いて、何かを抱きかかえているみたい。ああ、小さな女の子だ。まだ小学校にも行っていないような、可愛い女の子…え!?どうしたの、どうしてあんなに揺さぶられても、声を掛けられても、あの子、返事をしないの?目を覚まさないの?) 雅子の眼前で、長い髪の少女が立ち上がった。腕に幼い女の子を抱えたまま。女の子の赤い服が目にしみる。だらりと垂れ下がった幼女の手足。閉じられた瞳。血の気を失った小さな唇。 「あなたの、あなたのせいでこの子は殺された!返して!この子の命を返してよ!」 眉の線で切りそろえた前髪の下から、悲しみと憎悪に満ちた眼差しが雅子を射る。たじろぐ雅子は、怒りに震える美しい少女の顔を見て、その名を呼ぼうとして…
「津村…沙世子!」 うめきながら、雅子は目を覚ました。全身脂汗に塗れていた。激しい動悸を押さえて、辺りを見回す。いつもの自分の部屋…しかし何か違和感が… 立ち上がって、自分がシャープペンシルを握りしめていることに気づいた。机の上を見下ろす。 ノート一面に、いや、紙の上からはみ出してまで、芯が折れるほど書き殴ったおびただしい線。 ねじくれ、うねり、くねったその線から浮かび上がるのは、無数の蛇とも、一匹の龍とも見えた。
25 終夜営業のファミリーレストラン。郊外のありふれた店だ。北条寺美緒がその扉を潜ったのは午後十時を過ぎていた。 待ち受けていた仲間たちが一斉に挨拶してくる。皆、未成年の男女だが、酔いに顔を火照らせている。テーブルの上には食べ散らした料理の皿と飲みかけのグラスがいっぱいだ。携帯電話を交えた無秩序なお喋りが美緒を飲み込む。 美緒は何もしない。仲間たちの中身のない話を熱心に聞いてやり、全部の勘定を持ってやる。自分自身はほとんど酒も飲まないし、煙草も吸わない。ときにはどこで調達してきたのか覚醒剤や麻薬を仲間たちに回すが、自分はやらない。美緒にとっては、仲間たちが酔いどれ、自分を見失い、崩れていくのを観察することが面白いらしい。少年たちが酔いつぶれ、少女たちが喋り疲れていくのに反比例して、美緒の顔は精気を増していく。 午前一時。数人の女性たちが店に入ってきた。カラオケで喉を潰したらしい声が響く。皆、二十歳になったばかりの年頃か…中の一人は、四歳くらいの女の子を連れている。席に着くなり、女性たちはてんでに注文をしたが、女の子は母親らしい女の手をしきりと引っ張っている。 「ママ、うちに帰ろう。もう、うちに帰ろう」 母親は、仲間と夢中で喋り始めていて、女の子を相手にしない。そのうち、女の子は叫び始めた。母親は細く描いた眉を吊り上げて立ち上がり、強引に女の子をトイレめがけて引っ張っていく。 北条寺美緒は、不思議な表情で母娘を見ていた。怒りと懐かしさとが入り混じった、気高いとすら言えそうな顔で。そして席を立ち、母娘を追って行く。 トイレの個室から、母親の叱責の声と女の子の泣き声が漏れていた。「いつもいつもママの邪魔ばかりして、あんたなんか生まれなければ」 美緒は、すっと手を伸ばし、軽くジャンプして、トイレのドアの上辺に手を掛けると、ふわりと伸び上がった。足は完全に床を離れ、浮遊して真上から、母娘を覗く。長い髪がトイレの中に垂れ下がる。 泣いていた女の子が美緒に気づき、目を丸くした。「何を見てるの!」と怒鳴った母親が、上を見上げて凍り付く。美緒は、女の子に向かって、茶目っ気いっぱいのウインクを送った。女の子は驚いてはいたが、小さく答えた「こんばんは、おねえちゃん」 絶叫があがり、母親は娘を固く抱きかかえてトイレを飛び出し、仲間たちを見向きもせずに店を走り出た。 トイレの鏡に顔を映して美緒は呟く。 「あの子はきっと、朝までママに抱いていてもらえるね…あした世界が滅びると知れば、どの家族もみんな、仲良く最後の晩餐を囲むだろうね」 曇りのない美貌を囲んで、髪がうねる様に揺れた。
26 次の日、一美が登校してきたのは四時限目。宗教の授業だった。 教壇に立つシスター(修道女)は何人か居るが、概して生徒に心を開かず、一方的な授業を進める者が多い。私語でざわめいていたりすると、「静かになるまで授業を始めません」と言ったきり、目をつぶって一時間、教壇に立ったままのシスターもいる。 しかし、宗教を教えるシスター福永は、温かい人柄と内容豊かな授業で生徒に人気があった。四十歳くらいの年令で、背が高く、知的な美貌に憧れる生徒もいる。 「…だから、禁欲ということは大切なのです。人間はね、欲望に果てがないわけ。好きなままに欲望を満たそうとし続けると、たちまち限度を超えてしまうの。歴史を振り返ると、欲望のために破滅した人はいくらでも見いだせます…というより、テレビのワイドショーを見たほうが、手っ取り早そうね」 生徒たちがどっと湧く。 「大ざっぱに言うと、校則も、禁欲のためのものです。特に若いあなた達は欲望に負けやすい…でも、近頃は大人の方がそうかも知れないわねえ」 「はい!シスターの中にもお化粧に夢中な人が」お調子者の生徒が得意そうに言う。こういう台詞は、かれんがよく言ったものだと、雅子は彼女の空席を見て寂しく思った。 「こらこら…お化粧といえば、花宮さん、素敵な色のアイシャドーだけど、クラス委員のあなたがそれでは…、感心しませんね」 不意に名指しで注意されて、雅子は緊張する。福永は笑顔である。 「その色、鳴滝さんとお揃いみたいね。京都で流行ってたの?そういうお化粧」 一美は澄ました顔で首を振る。全く動揺していない。 「いいえ、これは古代エジプトで流行った色…いいえもっと遥か前、天使アザゼルが初めて人間に化粧を教えた時の色です。『エノク書』によれば」 教室が静まり返った。福永は目を細めて一美に問いかける。 「えのくしょ?何のことです、それは?」 「ご存じやないのですか?旧約聖書の外典ですけど」 福永はしばらく呆気にとられていたが、すぐに笑顔を取り戻す。 「変なウンチクでごまかそうとしてるのかしら…。鳴滝さん、あなたもこの学院の生徒なのだから、校則を守ることは義務なのよ。アイシャドーや口紅もそうだけど、一寸さっきから私、気になってるの」 福永は、ゆっくりと一美に向かって歩いて行く。狙いを付けた猫のような足取りだ。 「私、とっても鼻が利くのよ。あなたの髪…」 一美は立ち上がり、福永と間近でにらみ合う。二人とも身長はほとんど同じだ。 「昼休みに、生徒指導室…いいえ『告解室』にいらっしゃい。クラス委員と一緒に」 福永がそういい捨てて、きびすを返すと同時に、終了のチャイムが鳴った。
27 告解室は礼拝堂の中にあって、懺悔をする場所である。シスターたちが、校則を違反した生徒を見つけると好んで呼びつける場所だ。雅子は重い足取りで一美と並んで廊下を歩く。 「やっぱり、目立つよ。アイライン引いてシャドー付けるなんて」 「でも、花宮さんの肩、軽うなってるやろ?今まで、美緒の凶眼のせいで、相当消耗してたはずや」 「それは…そんな気もするけど。でも、なんなんだろ?一美さんの髪の毛とか、シスター言ってたけど」 雅子は、ストライドの長い一美の歩幅に合わせるのに苦労しながら呟く。一美はまっすぐ前を見たまま、無表情に答えた。 「煙草が匂ったんやろ。教室に入る前、ストレス溜まって一服吸うてしもたから」 「た、たばこお?」 思わず立ち止まり、雅子は一美の肘を掴んでしまう。一美はびくっと震えて身を固くする。 「なんでそんな、時代遅れのものやってんのよ!一美さんみたいに頭のいい人が、知らないわけないでしょ?煙草なんて身体にひどい害があるだけで、何にもいいことないじゃない!」 一美は雅子の手を邪険に振り放し、顔をしかめて歩き出す。 「…教室で授業受けるなんてストレスをそのまんまにしてる方が、私には体に悪いんや!」 「まさか、まだ持ってんの?煙草」 雅子が小声で尋ねると、一美は膨れ面のまま頷く。 「やばいよ…どっか、捨てていこうよ…」 「美緒の手下が尾けてるわ。あいつらが拾って、告解室とやらに届けに来るで」 「うぇ?」 雅子は慌てて振り向く。二十メートルほど後ろに、二人の同級生が、雅子たちと同じスピードで歩いていた。ぞっとして一美を追う。廊下は切れて校舎の外に出る。屋根付きの通路が、体育館や礼拝堂を結んでいる。昼休みの通路は、食堂に向かう生徒や、弁当を持って校庭に出ようとする生徒で混んでいた。 「じゃあ、せめてあたしに渡してよ。あたしが持ってれば…」 「あかんわ!ほっといて」 うるさそうに、足を早めた一美が、急に立ち止まった。その背中にぶつかりそうになり、雅子は慌てる。 「どうしたの?」 「…その、告解室って…どっちやの?」 ばつが悪そうに肩をすくめた一美に、雅子は思わず吹き出した。
28 改めて眺めると、この礼拝堂はなんだか不思議な建物だと雅子は思った。 (どうして、こんなに悪魔チックな飾りや彫刻が、あちこちにひっついてるんだろう) 急傾斜の屋根の下、高い壁から突き出すように、角を生やした人間の首や、ライオンや鷲の頭をした怪物、蛸のような魔物など、おびただしい奇怪な彫刻が礼拝堂を彩っていた。 一美は雅子と並んでそれを見上げながら、眉をひそめる。 「なんやの?…このガーゴイル?こないにギョウサンの魔除けで、悪霊追い払わなあかんほど、この建物を造った人は怯えてたわけなん?」 その言葉の意味を問いただす暇もなく、一美は魔物や天使、聖人たちの装飾で一杯の扉を開け、礼拝堂に入っていく。告解室は十字形の建物の、右の翼にある。 この部屋に足を踏み入れるのは雅子も初めてだ。シスターと顔を合わせずに話せる仕掛けがあるのと予想していたのを裏切り、部屋は全く普通の造りに過ぎない。ただ、窓は鎧戸で閉じられ、昼なのに明かりが点いている。 シスター福永は、重々しい机の向こうで、立ったまま二人を迎えると、一美に手を差し出した。 「今も持っているのなら出しなさい。それとも鞄の中?」 一美は唇をまっすぐに結んだまま、ブレザーの上着の右下ポケットから、封を切った煙草の箱を取り出す。開いた口には百円ライターが詰め込んである。 「あなた、何度も美園で、停学処分を受けているでしょ?それなのに、また」 福永は大げさに溜息をついて、煙草を取り上げて抽出に仕舞った。 「担任の野木先生や校長先生と相談して、あなたの処分を決めます」 雅子は口出しせずにいられなくなった。 「シスター、あの、一美さんは、やっと登校する気になってくれてるんです。どうか、停学とかそういうことは…」 「あなたは黙っていなさい!」 福永の声がぴしりと雅子を打った。しかし、すぐに福永の表情が崩れた。どこか卑しい笑いが浮かぶ。 「そうね…このことは黙っていてあげてもいいのよ。ふたりが私と、ある約束をしてくれれば」 雅子も一美も不意を打たれて、立ちすくむだけだ。 「鳴滝さんと花宮さん…今後、いっさいつきあわないように」 「ええっ?シスター、今、なんて」 雅子は自分の耳を疑った。 「花宮さん。あなたは、他の子のお手本になるべき子なの。鳴滝さんみたいな子に影響を受けるのは最悪だわ。親しくするのは絶対におやめなさい」 雅子は反射的に叫んだ。 「出来ません!そんなこと、嫌です!」 その声の激しさに、福永は目を丸くし、一美もまた、驚いて雅子を見つめる。 「花宮さん、どういうことなの?あなた、なぜそんなに転校したばかりの鳴滝さんにそこまで執着するの?」 福永の目が偏執的に光って、追求してくる。雅子は、激しく首を振ってうつむいた。理由などない。ただ、一美と一緒にいたい。そう、心の底から熱望している自分に雅子は気づいた。
29 福永はしばらく雅子と一美を交互に眺め、やがて頷いた。 「そう…そういうことなのね、やっぱり」 シスターの白い頬に微笑が浮かぶ。一美の顔に激しい嫌悪の色が走った。 「心配していたとおりだわ…花宮さん、確かに鳴滝さんは綺麗な女の子だし、頭も良いし、あなたが憧れを抱くのはわかるわ。転校生って、それでなくても興味を引くしね」 雅子は、福永の唇の動きを、ただ呆然と見ている。 「野木先生は生ぬるい人だから、あなたに明かさなかったのね。この鳴滝さんは、あなたの手に負えるような子じゃないの。京都の美園女子高校ではね、喫煙どころか、友達を傷つけて…」 そう福永が言いかけたとき、唐突に床が振動した。壁の古ぼけたロッカーや本棚ががたがたと揺れ始めた。 「地震?…いいえ、これは!」 雅子の脳裏に、閃くように蘇る光景。あの夕暮れ、何の前触れもなく鳴り響いた、西浜中学の窓枠、奇妙な振動に怯えて叫んだ自分… 福永は机の下に潜りかけた姿勢で、凝固している。揺れる電灯の光がその蒼白な表情を奇怪に映している。福永の視線の先には、昂然と胸を張って立つ一美がいた。起こったときと同じ唐突さで振動がやむ。 「シスター福永は、花宮さんと二人だけでいろいろお話がしたいみたいやし、うち、これで失礼します!」 「一美さん!」 雅子の叫びに背を向けて、長身の少女は靴を鳴らして憤然と告解室をあとにした。 後を追おうとした雅子の手を、冷たく大きな掌が鷲掴みにする。 「放っておきなさい。あなたは鳴滝さんに関わってはいけないわ。それに…この機会にあなたに話したいことがあるの」 一美が察したとおりに、福永はあらかじめ雅子に言いたいことがあるようだった。福永の手の冷たさに、痺れたようになり、雅子は肩を押されて椅子に座る。福永は、しばらく黙って部屋を歩き回っていたが、やがて雅子の耳元に口を寄せて、ささやき始めた。 「私は、この学院の伝統と秩序を守るために、一つの組織を作ってきたの。そう、秘密結社って言っても良いわ。メンバーは、選び抜かれた生徒たち。私はその生徒たちを、『妹』って呼んでいるの」 雅子は、無感動に福永の顔を見返した。野木と言い、この福永と言い、聖アガタの教師たちは、どうして自分を当惑させることばかり言うのだ…雅子の胸にはゆっくりと怒りが湧いてきた。こんなところにいたくなかった。すぐに一美の後を追いたかった。
30 雅子は礼拝堂を飛び出した。唇を強く噛みしめ、目尻に滲む涙を手で拭う。 (あたしの、あたしの一美さんへの気持ちは、あんな汚いものじゃない!) シスター福永は言った。「妹」の一人になれと。容姿も成績も性格も、とびきり優れた生徒が「妹」に選ばれるのだと。「妹」の列に加われば、特別な地位が約束される。「妹」は羊たち=一般生徒を導く、エリート。学院の特権階級にして、甘美な快楽を共有… 全部聞かずに、雅子は福永の手を振り払い、椅子を蹴るように立ち上がった。椅子の足が福永の向こうずねを強打して、シスターは悲鳴を上げてうずくまった。 (あたしは、あたしは一美さんに…) 何を求めているのかわからなかった。だが、今は、その姿を追わずにいられない。雅子は1Dの教室に駆け戻った。弁当を開いている級友に、一美の行方を尋ねる。鞄を持って出ていったという言葉に、雅子は返事もせずに教室を出ようとした。 ふわり、と黒い影が動き、出入り口を塞ぐ。北条寺美緒の笑顔が、雅子の足を凍らせた。 「クラス委員、どこに行くの?もうすぐ昼休みは終わりだよ」 アイシャドーを塗ったまぶたが熱い。雅子は必死に美緒の視線をはねかえす。美緒は雅子にくっつきそうなほど顔を近づける。 「報告しなよ、シスター福永は、何のためにあの転校生を告解室に呼んだんだよ?」 「あなたには関係ないよ」 「それは通らないんじゃない?クラスメイト一人の問題は、クラスみんなで考えるべき問題…とか前にあなた演説したじゃない。鳴滝さんに何か問題があるなら、あたしたちみんなで考えてあげなきゃあ…ねえ?」 美緒が顎をしゃくると、周りの生徒たちが、一斉に賛同の声を上げる。 「そうよそうよ」「クラス委員は、みんなに報告する義務があるわよ」「情報公開!」 雅子は信じられなかった。美緒の取り巻きだけでなく、教室にいる全員が、残忍な好奇心に目を光らせて、雅子を取り囲んでいた。 「みんな、いったいどうしたの?一美さんのことは…野木先生から説明…」 雅子の言葉は激しいブーイングにかき消される。 「鳴滝さんの校則違反て何だったの?」「話せよ!けちけちせずに」「どうしてまぁは鳴滝さんをそんなにかばうの」「もしかして、いい関係?」「まっさかあ」「同じ色の口紅」「同じアイシャドー」「喫茶店で一緒にいたって」「鳴滝さんの家にも行ったらしいよ」「うわあ、どうして?」「もしかして」「好きなんだ、あの転校生を」 言葉の渦の中で、雅子は耳を押さえてしゃがみ込む。激しい動悸が、胸を破りそうだ… いきなり、級友たちの責め言葉の嵐がやんだ。誰かの、暖かい手が、そっと雅子の肩に掛かり、ゆっくりと揺さぶる。雅子は、ぱっと顔を輝かせる。 (この優しい手は…一美さん?)膨れ上がる喜びと一緒に、雅子は顔を上げた。 そこに、北条寺美緒の、戦慄的なまでに美しい笑顔があった。 「ごめんね、花宮さん…ちょっとだけ気になったの。あなたが変に転校生に深入りしてるから…ねえ、教えて、あの転校生、あなたの、なんなの?」 目眩と虚脱感、そして、底知れない恐怖が雅子を襲い、彼女は意識が薄れた。
31 一美は、校門の内側にいた。外に出ようとしていた。急に振り返る。脳裏に、悲鳴が響いている。 (花宮…!) しなやかな足が地面を蹴った。重い鞄を胸に抱きかかえ、全力疾走する。一美は一気に空間を跳んだ。陽炎のようにその姿は揺らめいて桜並木から消え、瞬時に1Dの教室の入り口にテレポーテーションした。 息苦しい、熱いざわめきが教室を埋め、その中心に、北条寺美緒がいる。彼女は、床にしゃがみ込み、白い手を伸ばしている。手の先には、うつぶせに倒れた少女。打ちひしがれたその姿は、まるで暴風に叩き落とされた小鳥みたいに、華奢でむごたらしく一美の目に映った。 胸の中に、巨大な炎となって怒りが燃え上がる。一美は鞄を投げ捨て、教室に踏み込みざまに叫んだ。 「北条寺!おまえ!花宮になにしたんや!」 弾けるように振り返った美緒は、目を輝かせて立ち上がり、あの凶悪な視線をぶつけてくる。アンチモンで描いたアイラインと、孔雀石やトルコ石を摺り潰して塗ったアイシャドーが、凶眼をそらすが、一美は全身に針で刺されたような痛みを感じ、歯を食いしばる。 教室の空気が膨れ上がった。風が起こり、生徒たちの髪を乱す。美緒の髪がざわざわとうごめく。一美の髪が旗のようにひるがえる。窓ガラスが、ミシミシと耳障りに軋んだ。目に見えない力が爆発寸前に圧をあげていくのを、誰もが感じて、悲鳴が上がった。 「おまえたち!何をしてる!」 男の声が割って入った。教材を抱えた野木が、異様な雰囲気に顔色を変えて叫んでいた。 「みんな席に着け!…誰だ?倒れているのは?」 雅子に走り寄る野木を見つめて、一美は全身に溜めた力をゆっくりと放散させる。美緒が、ちらりと歯を見せて笑い、自分の席に戻っていく。溜息に近い、声にならないざわめきとともに、教室の緊張は失せた。 野木が雅子を抱き起こそうとしているのを見て、一美は素早く近寄った。野木の腕をさりげなく払いのけ、雅子をかかえあげる。 「保健室にいきます」
32 泥沼から這い上がる夢…もがきながら、雅子は目覚めた。ブレザーは脱がされ、ネクタイもなく、ブラウスの胸のボタンがいくつかはずされていた。 「ほら、気が付いたよ。疲労と精神的緊張のせいだ。もう大丈夫」 保健室にいつも詰めている女医の橘が、頑丈な身体から太い声を出す。ベッドをのぞき込んでいた女生徒が、ほっと安堵の息を付いた。宮前香奈だった。 雅子は首を振る。ひどく頭痛がする。 「今…何時?」 「午後二時ちょっと前。…まだ寝てた方がいいよ」 香奈があまり抑揚のない声で言う。まるっこい顔に、不機嫌そうな表情。いつもと変わらない。雅子は、なにを尋ねるか迷いつつ、思いついたことを口にする。 「クラスのみんなは、どうしてるの?」 「自習。野木先生は鳴滝さんのことを話し合ってる。シスター福永や校長先生たちと」 「一美さんは!?」 「礼拝堂で待たされてる。処分が決まるまで」 橘が、点滴の準備をしているのを見ながら、雅子は毛布をはねのけて起きあがった。 「もう大丈夫です」 「駄目!まだひどいよ顔色。」 思いがけない香奈の強い口調だった。橘は有無を言わせず点滴を雅子の腕に刺す。 「ご家族が迎えに来るから、それまで寝てるんだ。じゃ、あたしは校長に報告してくる」 そう言うと、橘は保健室を出ていった。 雅子は、爪を噛みながらしばらく天井を見ていたが、ふと、香奈に視線を向ける。自分でも思いがけない言葉が雅子の口をついて出た。 「ねえ…香奈、香奈は、野木先生のこと…好きなの?」 香奈は、激しく瞬きをした。唇が、震えた。何か言いそうになって、しかし、口をつぐんで顔をうつむけた。 「あたし、わけわかんないことばっかだよ。野木先生も、シスター福永も、…美緒も、なに考えてるんだかわかんない」 雅子のつぶやきに、香奈は顔を上げた。震える唇が、とぎれとぎれに言葉を吐き出した。 「美緒に…操られてる。野木先生も、シスター福永も、私も…、」 雅子は息を飲み、香奈の表情を窺う。いつもの無表情が崩れて、苦悩と恐怖がむき出しになっていた。 「私は野木先生が中等部の頃から好きだった。でも先生を好きな子なんていっぱいいる。千明やあおいみたいな美人に、私なんてかないっこないし、先生だって私なんか…あの時、先生が私を抱いてキスしたのは…魔が差したのよ。先生、美緒のせいで精神が動揺して…」 香奈がわなわなと震え始めた。雅子は思わず腕を伸ばして香奈の手を握った。 「ねえ、ずっと聞きたかったんだ。香奈って美緒と中学でもクラス一緒だったんだよね。美緒は、ずっとあんな風なの?どうして、あんなに…壊そうとするの?」 香奈は雅子の手を強く握り返す事で、身体の震えを止めようとしているようだ。 「私、中一の時から、いじめてたのよ。美緒を。いじけて暗い顔してたから、あのころの美緒。それが、春休みが終わって、中二の新学期になったら、まるで人が違ってた。誰も美緒をいじめるなんて出来なくなった。先生たちまで、怖がるようになった」 「その春休みに、なにがあったんだろ…」 「それは…噂よ、もう誰も口にしなくなった、噂だけど…美緒、黒い聖母に会ったんだって。そして魔力を授かったって」 「黒い聖母って…香奈、それ信じてるの?」 「わからない…でも、私は他のことも知ってる。美緒はあの春休みに…」
|
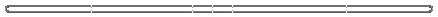
Copyright(c) 2003 龍3. All rights reserved.