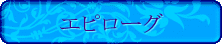
|
エピローグ・碧血碑 |
|---|
|
161 それは、薄れ行く意識の中で、自分が勝手に思い描いただけの、幻聴だったのか、礼子にはわからない。 (沙世子と私はひとつだよ) (そんなことができるの?) (やってみなよ、一美。きっとできるよ。あたしの中にカーリーがいたようにね) (あなたはいつも、わたくしをおどろかせるのですね、一美) (奈津、もうよかろう。一美はわしらの手を放れた。好きなようにさせよう) (礼子ちゃん、泣かなくていい。青い血なんていらないよ。私は秋やユキの中で、のほほんと生き続けるさ)
2002年初夏のその夜。気象常識を遥かに越える激烈な落雷で、江東区夢の島を中心に、都内の東半分は電気に関するほとんど全ての機構が壊滅した。停電と強い電磁波の影響で、コンピュータデータの多くが失われ、その混乱の復旧はいつになるかわからない。 同時に起こった夢の島の火災と破壊を目にした人間はかなりの数に上った。お台場や東京ディズニーランドから、間近に炎や爆発音を望めたからである。しかし、テレビ局や新聞社は、落雷による火災とだけ報道し、真相を掘り起こす事は全くなされていない。 ただ、噂や伝説が、おびただしく人の口から口へと広がっていった。 某国の秘密部隊が上陸して市街戦を演じたとかのたぐいが多い。だが、あるひとつの伝説は「光り輝く天使のような少女が、巨大な悪魔と戦い、世界を滅亡の淵から救ったのだ」というものだ。また別のひとつは「禁断の愛を貫こうとした娘が、天の怒りを買って雷電に焼き尽くされた」と語る。
礼子は夏休み直前に、ようやく登校することが出来た。 席替えがされていて、かれんの席も、一美の席も、もう痕跡はない。 あの出来事を、語り合える友は、誰もいない。 礼子は、教室を出ると、礼拝堂の裏手にある、深い森に足を踏み入れた。 苔むした地面に寝ころび、木々の間から空を仰ぐと、どこからか、懐かしい声がするような気がした。 礼子は深く息を吸い、静かに目を閉じ、じっと、耳を澄まし続けた。 (次回・エピローグ)
エピローグ ……翌年、初秋。赤石山脈の西側、天竜川の一支流のほとり…… 色づいた木々を縫って続いた登山道が、ようやく稜線に達して、視界が開けた。 沢渡礼子は、歓声を上げて、渓流を見下ろす谷間の景色に見入る。川のほとりには、校庭のような広場があり、数軒の家と畑、小さな牧場らしきものがそれを取り囲んでいる。「あれが三石川で、駒峰の集落なんだね」 礼子に並んで、細身の少年が額の汗をぬぐう。礼子は頷くと、彼の手を握りしめて、集落に続く坂道を、小走りに下っていく。 「礼子!」 弾むような声が、横手の森からあがり、籠を背負った長身の若い女が現れた。その後ろからは、見上げるような巨漢が、薪の山を担いでのっそりと続く。 「ワクラさん。ヘライさん。元気そうだね」 「礼子もね。で、彼が…」 「そう、唐沢由起夫。ユキって呼んで」 「あの探偵の息子で、今は礼子のカレシか」 ワクラは笑顔で、礼子たちを先導するように歩き始めた。小鳥の声と澄んだ日差しだけが降り注ぐ、平和で美しい谷間に。
「…幾つかの情報から推測出来るのは、キメラ・グループもまた、末端の存在として切り捨てられたと言う事実だ。あの事件後すぐにビースト捕獲・攻撃作戦の司令部は解散し、作戦要員も完全にバラバラになった。司令部長だったグループ幹部の一人は、ロッキー山中の別荘を要塞のように改造して立て篭もっていたが、9月下旬の夜、爆発が起こり、完全に別荘は消滅したらしい。どうやら、ビースト…魔王が手に入れた中性子弾頭を炸裂させたと思われる。それからのことは礼子も知っての通り、あの上院議員の汚職にはじまって、キメラグループの不正経理、政界との癒着が暴露されて、一年も経たずにグループは崩壊し、他の企業に寄ってたかって食いちぎられている。だが、魔王が敵と狙う、死の商人=巨大軍需産業体の悪龍のような本体は、未だびくともしてはいないのだ…」 礼子が渡した、アーサーからの便りを読んでいた麻田かれんは、不意に響き始めた赤ん坊の声に、手紙を置いて立ち上がる。ベビーベッドから抱き上げられた乳児は、あやすかれんの腕の中で、たちまち笑顔になる。 ログ作りの家の窓からは、廃校の校庭がよく見渡せる。ヘライに教えられながら、由起夫が上半身裸で、薪割りに苦闘している。簡易水道の水を溜めた水槽を囲んで、山菜や薬草を洗っているのは、ワクラたち魔多羅衆の女と、駒峰に元から居た老女たち。 「アメリカの大学に進むことを決めたのね、礼子さん」 香り高い自家製の緑茶を煎れながら、礼子に語りかけてきたのは、黒いセーターに長い髪を垂らした、五〇代の女性。赤石えりかの母親だ。えりかの祖母もこの家にいる。子育てをするかれんにとって何より頼りになる「二人のおばあちゃん」だ。 「はい。父の知り合いも多いし、潮田玲ちゃんも強く勧めてくれて」 「いいことだわ。そう…玲さんも、一度ここに呼ばなくてはね」 そのとき、授乳していたかれんが、リモコンでテレビを点けた。画面に、演説する合衆国大統領の姿が映る。同時通訳の音声が、ログハウスの天井に響く。 「…であるからして、テロリストが大量殺戮兵器を入手した…いや、している可能性は、限りなく高いのであります。よって我が国は、これに先制攻撃を掛ける権利を、断固として堅持しなければならず、核兵器の廃絶条約などという非現実的提案には、これを拒否する以外の道を知りません……」(エピローグはあと少し続きます)
溜息をついてえりかの母親が立ち上がり、かれんの抱く赤ん坊の顔を覗き込む。つられて礼子も立つ。 「ほんとに…可愛いね」 しみじみと礼子はつぶやいた。赤ん坊は驚くほど色白だが、健康そのもので、生き生きと光る碧い瞳は、誰をも魅了する。 「この子が成人するまでには、戦争をなくしておかなければね」 えりかの母親が静かに、でも力強く言った。 そのとき、赤ん坊の右手が小さな拳を握ったまま、激しく振られて、ある方向を指し示す。赤ん坊の顔には、はっきりと歓喜の色が浮かんでいる。 礼子は予感に駆られて、ログハウスを走り出た。由起夫やヘライのいる校庭を走り抜け、自分たちが来たのとは反対側の、高く天を突く山脈を見上げる。 やがて、稜線に現れた少女の姿。青空に浮かび上がる、美しいシルエット。長い髪が風に優美になびく。 礼子は、胸の中に熱いものが湧き上がり、その少女の名を呼ぼうとして…ためらう。だが、礼子を見て斜面を駆け下り始めた姿を見て、力一杯叫んだ。 「一美!」 「沙世子!」 いつの間にか礼子に並んでいた由起夫が、同時に叫んでいた。 走ってくる、透き通るような笑顔。見つめる礼子の眼に、その顔はやはり、二重写しに見える。 (あの時、轟く雷がやんだあとで、自分は沙世子と溶け合ってひとつになったのだ、と、一美は主張した。そして沙世子の遺体はみつからなかった) 息を切らして飛び込んできた少女の身体を、礼子はしっかりと受け止める。その熱さに、涙が溢れた。 (亡霊でも、怪物でもない。絶対に失いたくない、あたしの、ともだち) 「礼子、会いたかったよ」 その声は、やはり一美とも沙世子ともわからない。ただ頷くだけの礼子に代わって、由起夫が話しかける。 「汗かいただろ。今、風呂湧かしてるんだ。みんなで一緒に浸かろうか?」 礼子が目を剥いて由起夫に拳を向ける。 「ユキ、こら!」「わは、水着着てていいからさ」 笑いながら逃げる由起夫を、二人の少女が追いかける。いつまでもこんな時間が続いて欲しいと礼子は願っていた。(了) |

Copyright(c) 2003 龍3. All rights reserved.
